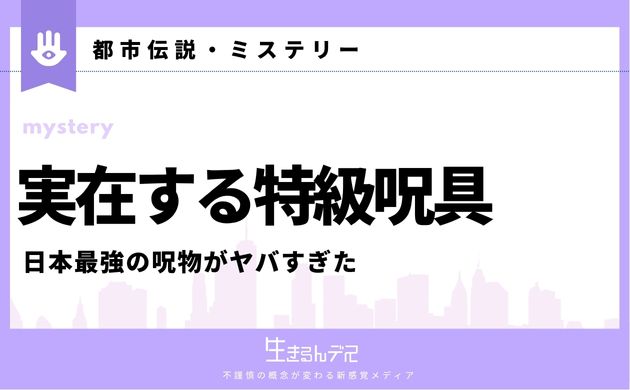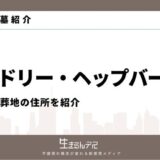特級呪具は漫画やゲームの世界だけのものではありません。
日本には強力な呪いの力を持つ特急呪具・呪物が存在し、歴史上にヤバすぎる数々の伝説を残しています。
この記事では、実在する特級呪具10選と日本最強の呪物を紹介しています。
実在する特級呪具10選|日本の呪われた刀たち
日本に実在する代表的な特級呪具と言えば、刀です。
多くの人の血を浴び命を奪ってきた刀は、驚異的な切れ味だけでなく、見る人の心を惹かせるような怪しい美しさを放っています。
まず、実在する特急呪具と言われる、呪われた刀達を紹介しましょう。
妖刀村正(ようとうむらまさ)
ゲームなどにも登場する、有名な特級呪具、妖刀村正。
村正とは何代も続いた刀工の名前で、彼らが作った刀の総称です。
切れ味の良さで評判の村正は、時の権力者や徳川家康の祖父、妻などに死をもたらしました。
家康自身も傷を負ったため、災いをもたらす刀とされ徳川家からは忌み嫌われました。
しかし、その怪しさにかえって魅力を感じた人も多く「人の心を乱す刀」として歌舞伎に登場したり、幕末の志士、西郷隆盛に愛用されたりしています。
草薙剣(くさなぎのつるぎ)|天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)
草薙剣と呼ばれる場合と、天叢雲剣と呼ばれる場合がありますが、同じ刀のことで三種の神器の1つとして、形代が宮中に祀られています。
日本神話に登場する最古の特級呪具で、スサノオが出雲国でヤマタノオロチを退治した際、大蛇の体内から見つかった神剣です。
また、ヤマトタケルが敵の放った野火に包囲された際、この刀で草を刈って脱出したなど、多くの伝説がある刀でもあります。
天逆鉾(あめのさかほこ・あまのさかほこ)
呪術廻戦に登場する刀と異なりますが実在する特級呪具で、宮崎県の高千穂峰の山頂に突き立てられています。
地上に出ている部分は火山で折れたため、現在刃の部分はレプリカで、埋まっている柄の部分だけが本物だそうです。
この逆鉾を抜くと災いがあると言われていますが、坂本龍馬がこの地を訪れた際、一度引き抜いて戻したと言われています。
その後、坂本龍馬は若くして亡くなり、逆鉾の周辺でも天災が続きました。
鬼丸国綱(おにまるくにつな)
鎌倉時代に刀工、粟田口国綱が作った特級呪具で、天下五剣の1つとして、現在は宮内庁が管理しています。
北条時政が夢の中で小鬼に苦しめられていた時、夢に現れた老人が「自分は刀の化身で、刀の錆を落としてくれたら小鬼を退治する」と言ったのです。
時政が刀の錆を落として柱に立てかけておいたところ、刀は自然に倒れて、火鉢の足に施された小鬼の首を切り落としたことから、鬼丸国綱と呼ばれるようになりました。
雷切(らいきり)
戦国時代の武将、立花道雪が雷(雷神)を切ったと言われる、特級呪具です。
道雪が木陰で休んでいたところ、夕立が降り始め雷が落ちかけたため、手元にあった刀で雷を切ったという逸話から、雷切の名前がつきました。
道雪はこの落雷が原因で半身不随となりましたが、雷切を使い武将として誰よりも活躍しました。
立花家資料館に残る雷切には、実際に雷に打たれたような、変色した部分があると言われています。
祢々切丸(ねねきりまる)
全長324センチメートル、刃の長さは216センチメートル、重量24キロという巨大な刀で、作者も使った武将も明らかにされていない特級呪具。
かつて日光の山中にネーネーと嗚く化け物(祢々)が出るようになり、人々が困っていたところ、祢々切丸は勝手に鞘から飛び出して、化け物を退治してしまいました。
現在は日光二荒山神社の御神刀として大切に保管され、重要文化財に指定されています。
三日月宗近(みかづきむねちか)
天下五剣の1つ、三日月宗近は、細身で反りが強く美しい刀で、刃縁に沿ってかかる刃文が、三日月が浮かんでいるように見えることから名前がつけられました。
作者は平安時代の刀工・三条宗近で、多くの合戦で使われた特級呪具ですが、その妖力は持ち主さえも危険にさらすことがあったとか。
室町時代から将軍家に伝わる宝などとして伝承され、現在は国立博物館で保管されています。
岩融(いわとおし)
源義経の家来、武蔵坊弁慶が使っていたと言われる、伝説の巨大な特級呪具です。
作者は三日月宗近を作った刀工・三条宗近で、刃の長さだけでも106センチメートルあり、岩を断ち切るほどの威力を持つ、強力な薙刀(なぎなた)でした。
武蔵坊弁慶は、生まれた時が既に三歳児並の大きさで「鬼の子」と言われたほど、並外れた体格だったので、巨大な岩融を自在に扱えたのでしょう。
髭切(ひげきり)
平安時代に作られた名刀で、名前や持ち主を変えながら源氏に伝えられた特級呪具です。
まず、試し切りで罪人を切ったところ、首だけでなく髭も切れたことから「髭切」と呼ばれ、その後は鬼を切って「鬼丸」と呼ばれるようになりました。
さらに「獅子の子」「友切」と名前を変えるうちに、源氏は平家に敗れ落ちぶれてしまいます。
しかし、源頼朝が夢でお告げを聞いて名前を髭切に戻すと、源氏を勝利に導きました。
童子切安綱(どうじぎりやすつな)
天下五剣の1つで、平安時代の刀工安綱が作った特級呪具です。
源頼光が丹波の大江山に住み着く鬼、酒呑童子の首を切り落としたことから、童子切の名前がつけられました。
江戸時代には、罪人の死体を6体積み重ねて試し切りをしたところ、6体とも切れただけでなく、台まで刃が達したと言われています。
足利家から秀吉、家康、松平家と受け継がれ、現在は国宝として国立博物館で保管されています。
▶13日の金曜日、実は日本でも“不吉な日”のジンクスだって知ってましたか?
実在する…?最強呪物5選
日本には刀以外にも、強い呪いの力を持つ特急呪物が存在しています。
普段は見ることができなくても、強い力を持つ呪物として昔から大切に取り扱われている、伝説の呪物もあります。
次は、実在する日本最強呪物を紹介しましょう。
八尺瓊勾玉(やさかにのみこづくりのたま)
日本の皇位継承の象徴とされる三種の神器は、実在する最強呪物と言えるでしょう。
三種の神器とは、八尺瓊勾玉、次に紹介する八咫鏡、特級呪具の刀で紹介した草薙剣です。
八尺瓊勾玉は、周囲が八尺(約140センチメートル)の勾玉、または八尺の長さの緒がついた勾玉だと言われています。
八尺瓊勾玉は、天岩戸伝説で天照大神を岩屋から出すために使われた装飾品の1つで、現在では皇位継承の神聖な儀式で用いられます。
八咫鏡(やたのかがみ)
天孫降臨の際、天照大神から授けられた三種の神器、鏡・剣・玉のうち、鏡に当たるのが八咫鏡で、伊勢神宮で保管されている最強呪物です。
ちなみに剣に当たる草薙剣は熱田神宮に、玉に当たる八尺瓊勾玉は皇居吹上御所の「剣璽の間」に安置されています。
八咫鏡は神聖な存在として神霊が宿るとされ、真実を映し出すので誠実さと正義の象徴として、現在も裁判官のバッジのデザインになっています。
陰陽術願勾玉(おんみょうじゅがんまがたま)
陰陽術願勾玉は、陰陽師が正装する時に使う勾玉で、これを身につけると悪しきものが一切近寄れなくなるという、最強呪物です。
勾玉の形状は魂を象徴的にかたどったものとされており、材質は翡翠や水晶、瑪瑙などの天然石で、神の遣いと言われる鹿の革紐でつながれています。
材質、形状とも強力なパワーを持つものばかりですが、特に翡翠は術に使いやすい石として、陰陽師によく用いられました。
殺生石(せっしょうせき)
栃木県那須郡の那須湯本温泉の近くにある溶岩で、今でも近くでイノシシやタヌキなどの死体が見つかることがある、日本最強呪物です。
伝説では鳥羽上皇が寵愛した玉藻前が、陰陽師に九尾の狐であることを見破られ、追い詰められて殺傷石に姿を変えたと言われています。
石になっても毒を発して命を奪い続けたため、源翁和尚によって砕かれたのですが、かけらが全国に飛び散ったため、全国各地に殺傷石伝説が残されています。
コトリバコ
都市伝説として有名になった、日本に実在すると言われる最強呪物です。
江戸時代の末期に山陰地方のとある集落で、自分たちを迫害する人の一族を根絶やしにするため、呪いをかけて作ったのが最初のコトリバコだと言われています。
コトリバコは流産した子供の遺体や、殺された子供の身体の一部を入れて作った呪いの箱。
送られた人が呪いを受けると内臓が引きちぎられて、苦しみながら死んでしまう、恐ろしい呪物です。
【呪術廻戦の心に刺さる名言はこちら】
 呪術廻戦の心に響く名言集!キャラクターたちの信念が詰まったセリフを厳選
呪術廻戦の心に響く名言集!キャラクターたちの信念が詰まったセリフを厳選