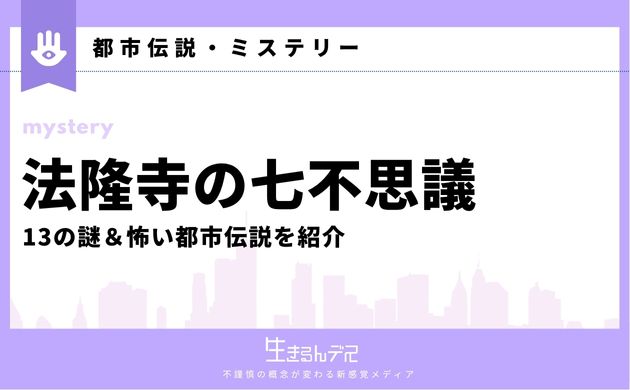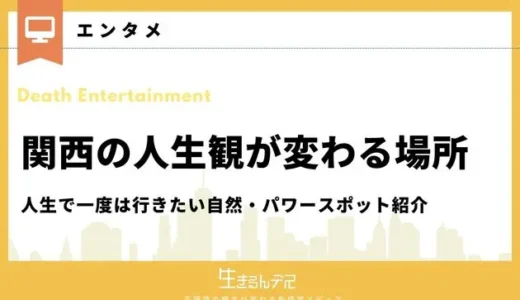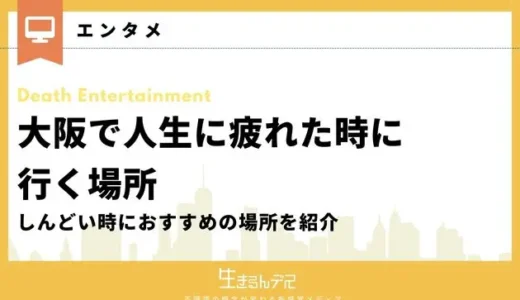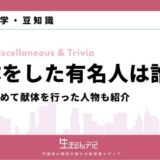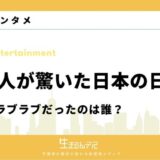1400年以上の長い歴史を持つ法隆寺。
歴史と伝統を感じさせ、現在も多くの人が観光で訪れています。
そんな法隆寺には、七不思議があるのを知っていますか?
長い歴史や背景から伝わる数々の伝説が、現地に訪れた人々の関心を高めていることに間違いありません。
この記事では、法隆寺の七不思議を紹介!
未だ解明されていない13の謎や、怖い都市伝説を解説します。
法隆寺の七不思議その1:蜘蛛の巣が張らない
法隆寺の七不思議には「蜘蛛が巣を張らない」というものがあります。
蜘蛛は天井や四隅、樹木や壁の隙間など、あらゆるところに巣を張るイメージを持つ人も多いでしょう。
法隆寺に蜘蛛が巣を張らないのは、神秘的な空気感からなのか、それとも時空を超えたパワーが宿っているからなのか…。
一説には、法隆寺の木材や、建築方法に秘密があるのではないかとも考えられています。
古代の建築技術による通気性や湿度の調整が、蜘蛛にとって巣を作りにくい環境を生んでいる可能性があるのです。
しかし、現在法隆寺では、蜘蛛の巣が発見されています。
このことから、法隆寺の七不思議「蜘蛛の巣を張らない」というのは言い伝えであり、多くの人を惹きつける魅力の1つとなっています。
法隆寺の七不思議その2:鯛石を踏むと水難を免れる
法隆寺の七不思議として知られている魚の形をした「鯛石」。
鯛石を踏むと、水難を回避できるといわれています。
昔、大和川が氾濫し大洪水が発生しましたが、鯛石よりも奥には水が流れてこなかったそうです。
川や海の事故から免れたり、水害から守ってもらえたりするという教えがありました。
近年では、旅行や行事に参加する際に、鯛石を踏みに訪れるという人もいるのだとか。
どれだけの効果を発揮するのかはわかりませんが、法隆寺の魅力の1つとして、これからも鯛石の存在が多くの人に安心感を与えてくれるでしょう。
法隆寺の七不思議その3:法隆寺の石は雨だれで削れない
法隆寺の七不思議のなかには「雨だれの跡がない」という奇妙な話も。
1400年以上も前に創設されているため、何度も雨風にさらされたでしょう。
雨だれの穴が開いていないのは、一般的な家に比べて屋根が高い位置にあることが関係しています。
地面に落ちる前に風にあおられて、同じ場所に雨が落ちないから…といわれているのです。
また、一部では法隆寺の神秘性を裏付けるための物語として広まったのでは…?という説もあります。
実際、法隆寺には穴が開いた石が確認されており、真実とは言い難いからです。
しかし、どちらにしても神秘性や荘厳なイメージを生み出したことに変わりはなく、法隆寺の七不思議に相応しいといえるでしょう。
法隆寺の七不思議その4:西院伽藍中庭には3つの隠し蔵がある
法隆寺の七不思議の1つに「西院伽藍中庭には3ヶ所に隠し蔵がある」といわれています。
隠し蔵には財宝が保管されているとされ、地主神を鎮めて建物の安全を祈る意味が込められた「鎮壇具(ちんだんぐ)」が納められたそうです。
一説によると、この場所に財宝を納めるよう指示を出したのは、聖徳太子なのだとか。
当時は、僧侶が聖徳太子の深い信仰心に基づき、財宝や鎮壇具を保管するための特別な場所として、この空間が設けられたと伝えられています。
真相はわかりませんが、隠し蔵があるという話は、長い歴史のなかにある知恵が垣間見える七不思議だといえるでしょう。
法隆寺の七不思議その5:五重塔には鎌が刺さっている
法隆寺には「五重塔に鎌が刺さっている」という七不思議も!
五重塔の先端に九輪と呼ばれる飾りがありますが、この九輪に4本の鎌のようなものが置かれているというのです。
一説によると、怨霊封じや魔除けとして置かれているのだとか。
しかし、実際は避雷針だとされており、怨霊封じや魔除けではないようです。
独特な見た目から、このような言い伝えが広まったのかもしれません。
とはいえ、七不思議として残り続けているのも、法隆寺そのものが神聖な場所だからこそ。
単なる避雷針ではなく、長い歴史の背景や伝説が融合しており、法隆寺の価値を改めて考えさせられる七不思議です。
法隆寺の七不思議その6:因可池(よるかのいけ)のカエルは片目がない
法隆寺には、因可池にいるすべてのカエルが、片目しかないという七不思議もあります。
カエルの鳴き声が学問の妨げになると感じた聖徳太子が、筆を池に投げ込むとカエルの目に当たったというのです。
学問を重んじる聖徳太子にとってカエルの鳴き声は、集中力の低下に繋がり、邪魔だったのでしょう。
この話から「学問に集中するためには、余計なものを排除すべき」という教えが込められているのでは…?とも考えられます。
その後、カエルは聖徳太子に許してもらいたい一心で片目になった…という伝説の話が有名です。
現在、因可池にいるカエルは両目があるため、伝承として広まったものだとされます。
法隆寺の七不思議その7:夢殿の礼盤はいつも汗をかいている
法隆寺の七不思議には「お坊さんが座る礼盤が常に汗ばんでいる」という奇妙な説もあります。
日に当たると、板の裏から溢れるように水が出てくるといわれているのです。
その年が豊作かどうかを占う儀式で、汗が出たら豊作だと考えられていました。
しかし、実際の礼盤は乾いているようで、お坊さんが座る礼盤が常に汗ばんでいるという事実はないようです。
一方で、木材が湿気で湿った状態を「汗をかく」という表現に変換された可能性も否定できません。
現代の視点で見た解釈にはなりますが、通常礼盤が乾いているため、木材の性質から伝説が生まれたともいえるでしょう。
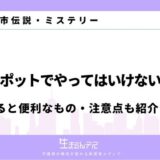 心霊スポットでやってはいけないこと8選!準備すると便利なもの・注意点も紹介
心霊スポットでやってはいけないこと8選!準備すると便利なもの・注意点も紹介 七不思議には続きがあった!法隆寺にまつわる謎&都市伝説
法隆寺の七不思議は、これだけでは終わりません。
この記事で紹介した奇妙な出来事には、続きがあるのです。
ここでは、法隆寺の七不思議にまつわる謎や、都市伝説を紹介します。
法隆寺には雀が糞をしない
法隆寺には、雀は糞をしないという説があります。
通常、寺院や神社では鳥が飛び交っており、糞害等の問題が発生していることは否めません。
法隆寺の七不思議として「蜘蛛が巣を張らない」という言い伝えがありますが、それだけ聖なる場所であることの象徴だといえるでしょう。
長い歴史を持つ法隆寺の特別な環境から、生み出された物語なのかもしれません。
このような伝説が本当なのかを確認しようと、現在も多くの人が現地に足を運んでいます。
キトラ古墳と若草伽藍と鯛石を結ぶ謎
鯛石は法隆寺南大門前の参道中央にある石ですが、若草伽藍(創建時の法隆寺とされる寺院跡)の軸線と関連するされ、特別な配置だと考えられます。
この配置には仏教的思想が反映されている可能性があり、キトラ古墳(2番目に極彩色壁画が発見された古墳)との繋がりも指摘されているのだとか。
法隆寺とキトラ古墳には、現在も未解明のままになっているものが多く、謎に包まれています。
しかし、鯛石が法隆寺の歴史や文化を知るうえでの、重要な鍵になることはいうまでもありません。
キトラ古墳との関わりが明確になれば、理解の深化に繋がるでしょう。
金堂・五重塔の裳階(もこし)は1世紀後に生まれた建築様式
世界最古として知られている法隆寺ですが、その建築仕様には未だ解明されていない、多くの謎があります。
なかでも、金堂や五重塔の裳階は8世紀以降の様式とされていますが、これは法隆寺の創建時期とは異なる矛盾点の1つです。
金堂や五重塔の建築様式を分析すると、法隆寺の創建当初に見られる裳階とは異なるものであることがわかっています。
この不一致は、建築史研究における重要なテーマであり、注目すべき課題だといえるでしょう。
建築上あり得ない中門の間口4間の造り
中門は、法隆寺西院伽藍の入口に位置し、間口4間という独特の構造を持ちますが、中央に柱があるため出入りしにくく不便です。
中央の柱は、通行や門としての役目を果たすうえで、建築基準を考慮したとしても非合理的な構造になっているのです。
しかし、中門の構造は入口を目的としていないのでは…?という説が浮上。
「聖徳太子とその一族の魂を鎮めるために、あえて区切りが設けられた」といわれてます。
一見不便な構造ですが、法隆寺は仏教の聖地であることから、特別な意味を持つとされているのです。
五重塔から消えた仏舎利
法隆寺五重塔には、仏舎利6粒と髻髪(まゆどり)6毛が納められていました。
しかし、かつて納められていた仏舎利が現在では確認できません。
仏舎利とは釈迦の遺骨や遺灰を指し、それが安置されているということは、それだけ法隆寺が霊的なパワーが宿る場所であることの象徴ともいえます。
鎌倉時代の記録にはその存在が記されていますが、大正時代には仏舎利がすでになくなっているのです。
この謎は未だ解明されておらず、法隆寺の神秘性を高めていることには違いありません。
日本最古といわれる法隆寺の歴史的な価値が、さらに人々の興味を集めることでしょう。
同じ場所に保管されていた髻髪は、一部残っていることが確認されています。
地上に突き出した伽藍の心礎
若草伽藍の心礎は通常、地中に埋まっていますが、心礎部分が外に出ており、地表に残されたままです。
誰かが若草伽藍の心礎を持ち去った後、戻しに来たものの、何らかの理由でそのまま放置されたのでは…という説が浮上しています。
法隆寺は神秘的な場所であることから、その場所に宿る霊力や強いパワーを得ようとして、若草伽藍の心礎を持ち去ろうとしたのかもしれません。
しかし、実際は解明されておらず、現在も法隆寺の七不思議として残り続けており、未解決のままです。
一方で、地殻変動によるものだという説も。
法隆寺がある奈良県付近は、古来より地殻変動や洪水などの災害を受けやすい地域でした。
このことから、若草伽藍の心礎が地上に押し上げられた可能性も否定できないのです。
【関西地域で行ってみてほしい場所!】