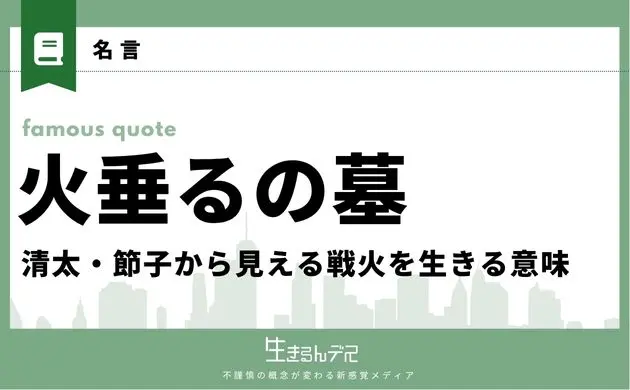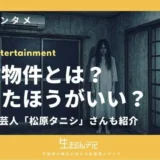本土空襲も多く、敗色濃厚な太平洋戦争末期の日本を描いた「火垂るの墓」。
子どもである清太・節子を軸に物語が進んでいき、戦時下の神戸を懸命に生きようとする姿に、胸を打たれた人も多いのではないでしょうか。
この記事では。火垂るの墓の名言・セリフを紹介します。
「火垂るの墓」の名言|清太のセリフ
昭和20年9月21日夜。ぼくは死んだ
映画の冒頭で清太が語るセリフです。
火垂るの墓は、清太が死ぬまでどんな過去があったのかを回想する作品。
命が尽き果てることを分かりながら作品を見るというのは、何とも言えない気持ちになりますね。
これおはじきやろ、ドロップちゃうやんか。
栄養失調のため意識が朦朧としている節子が、おはじきを舐めているのをみた際のセリフ。
食糧もないなか、ドロップはとても贅沢品でした。
そのためか、意識を失いかけながら節子が一番食べたかったのはドロップだったのでしょう。
おはじきを舐める節子の姿には言葉にはならない感情が湧いてしまいます。
滋養なんて、どこにあるんですか!
節子を病院に連れて行った時に医者から『滋養をつけなさい』と言われた際の言葉です。
食事もまともに摂れない状況下において、滋養なんてあるわけがありません。
その冷たい扱いに対して、清太は思わずこのセリフを返します。
しかし、当時は国民が皆大変な状況でしたので、とても「ひどい医者」なんて思えません。
そんなんゆうたかって、学校燃えてしもうたもん
疎開先の叔母さんに学校はどうしたのかと聞かれた際のセリフ。
学校に通うというのは平和の象徴です。
現代でも戦闘の激しい地域や国では、学校や教育システムが機能していない場所も多くあります。
めんどくさいながらも通学できるというのは、とても幸せなことなのでしょう。
「火垂るの墓」の名言|節子のセリフ
なんでホタル直ぐ死んでしまうん?
防空壕で清太が蛍を集めて、節子に見せてあげた翌日に出たセリフ。
蛍を集めて埋める節子を見て、自分の母が火葬されたことを思い出します。
焼夷弾で多くの命が散ったことを表す「火垂る」と、儚く消える「蛍」をかけたシーンでもあり、2人の死を表現し、日本中が「火垂る」の墓となっていたことを伝えています。
どこが痛いの?いかんね、お医者さん呼んで注射してもらわな。
食糧難によって清太は、農家の畑から野菜を盗むようになり、ついにばれてしまいます。
農家の男性に捕まった清太は、殴られてから警察に突き出されてしまい、その迎えに節子がきました。
その際に節子が清太に賭けた言葉です。
何をして清太がこうなったか知らず、純粋に心配する節子に心が揺さぶられます。
泳いだらお腹減るやん
清太に泳ぎ方を教えるといわれて、返した言葉です。
普通なら「別にいいよ」といった返答ですが、ここではお腹が減ることを理由に断ります。
4歳という年齢で食料がない状況をなんとなく分かっているのが、何とも辛いシーンですね。
お母ちゃんのおべべあかん。 お母ちゃんのおべべあかん!
おべべとは関西弁で衣服のこと。
清太と節子の母の衣服を売ってお米に替えようとする叔母に対して、節子が訴えるシーンのセリフ。
清太は母の死を分かっており、衣服を米にすることに概ね賛成ですが、4歳の節子に孫亜子とは分かりません。
まだ母が帰ってくると思っているため、衣服を置いておきたいのでしょう。
叔母の判断が正しいと同時に、どうしても子どもの気持ちも汲んでしまうため、見ていて悲しくなるシーンです。
火垂るの墓の名言・セリフは民間人から見た戦争の悲惨さを知れるものばかり
世界中に戦火が広がった第二次世界大戦では、各国の兵士・民間人が多く亡くなりました。
この日本でもたくさんの苦しみや悲しみが生まれてから、80年が過ぎました。
体験者が少なくなっている中、火垂るの墓は戦争の悲惨さを伝える作品であり、清太や節子の言葉から当時の状況が垣間見えます。
「過ちは 繰返しませぬから」を守るためにも、この記事で紹介した名言を覚えておきましょう。
【ジブリの名言集】