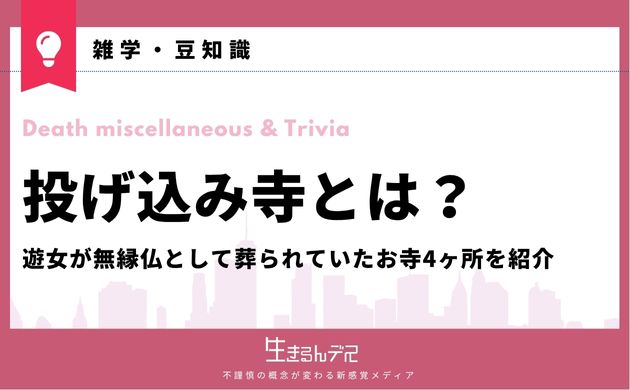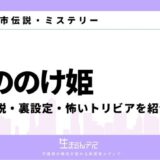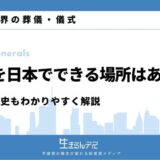現代でも耳にすることのある「投げ込み寺」という言葉。
なんとなく聞いたことはあるものの、意味や語源については知らないという人も多いでしょう。
この記事では、投げ込み寺の意味について解説します。
過去に多くの遊女が葬られた、現存している投げ込み寺についても紹介しますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
投げ込み寺とは?投げ込まれたのは遊女だけ?
投げ込み寺とは、身寄りのない遊女などが葬られていた寺院のこと。
無縁仏として穴に投げ込まれるように葬られていたことから「投げ込み寺」という俗称が広まりました。
過酷な環境下で暮らしていた遊女たちの平均寿命は22歳程度と非常に短く、性病などで命を落とした後は寺院に投げ込まれることが多かったそうです。
投げ込まれていたのは遊女のみならず、行き倒れの遺体や被災者なども投げ込まれていたとされています。
NHK大河『べらぼう』で話題になった
投げ込み寺という言葉が再注目されるようになったのは、NHK大河ドラマ「べらぼう」の放送がきっかけ。
べらぼうは、江戸幕府公認であった最大の色街・吉原遊郭で生きる遊女の過酷な生活やリアルな死後が描かれています。
遊女といえば、華やかな衣装に身を包んだ美しい花魁をイメージする人も多いでしょう。
しかし、吉原での生活は決して楽ではなく、年季(契約期間)中に死んでしまうと悲惨な末路を辿ることになるのです。
投げ込み寺だった寺院4つ
遊郭の華やかなイメージとは真逆の存在である「投げ込み寺」。
実は、投げ込み寺という俗称で呼ばれている寺院は、現在でも残されています。
こちらでは、投げ込み寺だった4つの寺院について解説。
現在でも参拝できる投げ込み寺と呼ばれた寺院はあるので、その場で安らかに眠る遊女たちにお参りしてみてはいかがでしょうか。
浄閑寺
投げ込み寺として有名なのが、三ノ輪(現在:荒川区南千住)にある浄閑寺。
浄閑寺は新吉原遊郭から近く、身寄りのない遊女たちが数多く葬られました。
寺院には遊女たちを供養する塔「新吉原総霊塔」があり、この地で眠る遊女たちの魂を慰めています。
また、新吉原総霊塔には、川柳作家・花又花酔が遊女たちに向けた呼んだ句「生まれては苦界、死しては浄閑寺」が刻まれていることでも知られています。
西方寺
東京都豊島区にある西方寺も、投げ込み寺として有名です。
移転前は吉原遊郭近くの浅草聖天町(現在:東京都台東区浅草)に位置しており、当時は「土手の道哲」と呼ばれていました。
有名な遊女である二代目高尾太夫の墓や、元禄時代に活躍した遊女の薄雲太夫と関わりの深い猫の逸話などもある寺院です。
海蔵寺
海蔵寺は、日本仏教の一つ「時宗」の寺院で、東京都品川区にあります。
遊女のみならず、獄中死・死刑となった罪人や身寄りのない人なども無縁仏を、供養する寺院としても知られていました。
海蔵寺には投げ込まれた遊女たちが安らかに眠れるよう、いくつかの無縁塔があります。
多数の無縁塔を祀っている通称「首塚」は、参拝すると頭痛が治るという言い伝えもあるそうです。
雲龍寺
雲龍寺は、東京都八王子市にある寺院で、かつては「本郷村の投げ込み寺」とも呼ばれていました。
明治時代に突入すると廃寺寸前まで衰退しましたが「三十六世 正山戒宗大和尚」により再興されました。
1963年開催の東京オリンピックに伴う区画整理で、八木町から山田町へと移転され現在も地元に愛される神社として知られています。