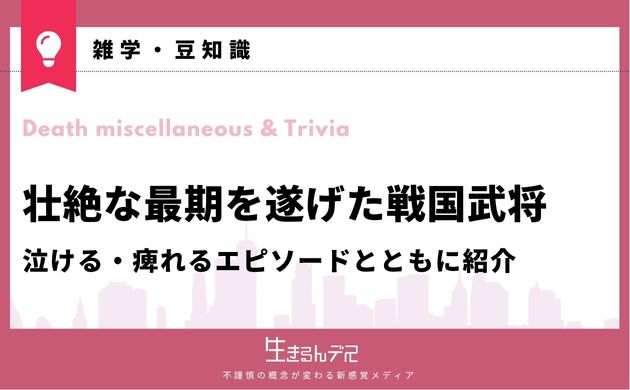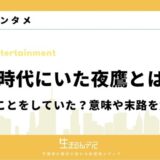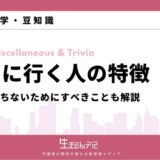戦国時代を生き抜いた武将たちは、命を懸けて戦い、平穏とはいい難い最期を遂げました。
これから紹介する戦国武将は、領土を守りつつ拡大させようと必死に戦い抜き、壮絶な死を遂げた人たちです。
この記事では、壮絶な最期を遂げた10人の戦国武将を紹介!
当時のエピソードを交えながら、壮絶な生きざまをお届けします。
763人が玉砕!最期まで気高く散った風神:高橋紹運(たかはし じょううん)
高橋紹運は、1548年に大友義鑑の重臣・吉弘鑑理の次男として誕生しました。
13歳で初陣を果たし、高橋家を継いだ紹運は、大友家の重臣として北九州の防衛に奮闘するも島津氏に敗北。
1586年の岩屋城の戦いでは、島津軍5万人に対し、城を守るのは紹運ら763人と、対等に戦える人数ではありませんでした。
重傷になっても諦めずに戦いますが、味方の数は減るばかり。
主従が数人になると、紹運は高やぐらに上り、自害で生涯を終えるのです。
紹運を見て、思わず涙を流したのが敵陣の島津忠長でした。
「類まれな勇将を殺してしまった。この人と友になれたなら、どれだけ嬉しいことだったろう。弓矢を取る身ほど恨めしいものはない」と。
壮絶な最期を遂げた戦国武将として、後世に名を残す見事な戦いぶりでした。
将軍の権威を守り華々しく散った剣豪:足利義輝(あしかが よしてる)
室町幕府の第13征夷大将軍「足利義輝」は、壮絶な最期を遂げた戦国武将の1人。
1546年、11歳の若さで父を継いで将軍になるも、すでに幕府の勢いは衰えていました。
それでも義輝は、以前の勢いを取り戻そうと奔走し、力を尽くします。
ところが1565年に、義輝に将軍退位を迫るべく、三好義継は1万人もの武士とともに御所を囲み、争いが始まったのです。
味方が討たれるなか、義輝には誰も手出しできないほどの活躍ぶりだったそう。
しかし、三好軍がスキをついて義輝の足を薙ぎ払い転倒させ、上から戸板を何枚も重ねてめった刺しにしました。
足利義輝は三好軍の攻撃により、壮絶な死を遂げたのです。
自らの臓物を投げつけた:三好元長(みよし もとなが)
三好元長は、政権奪取に貢献した勇将で、壮絶な最期を遂げた戦国武将として名の挙がる驚愕の死を遂げた人物です。
1526年に、元長と細川晴元は阿波で挙兵。
足利義維を支持して高国軍を襲撃し、近江へと追いやりました。
1531年、中嶋の戦いが起こり、大物崩れによって高国が敗戦。
この後元長は、政権内部の揉め事に巻き込まれます。
元長の実力は頭1つ飛び抜けていたので、出世を望む三好政長や木沢長政は、元長を追い落とそうという目論みがありました。
1533年には、長政がいる飯盛山城を包囲した元長ですが、太刀打ちできずに自害。
腹を切り、内臓を引きずりだして天井に投げつけるという、壮絶な最期だったといわれています。
伏見城の戦いに散った家康の忠臣:鳥居元忠(とりい もとただ)
鳥居元忠は、徳川家康から絶大な信頼を寄せられていた1人。
家康が上杉景勝の征伐に向かうことになった時、京都・大阪周辺には家康方の将軍がほぼいなくなる事態となりました。
家康は、豊臣秀吉に仕えた武士「石田三成」が挙兵することを勘づき、不在の間、時間稼ぎしてほしいと元忠に頼んだのです。
家康が出発した1ヶ月後、伏見城に三成が挙兵し、伏見城の戦いが始まりました。
4万の武士に対し、家康が伏見城に残した兵は1800人。
しかし、敵を城内に入れることすら許さないほどの奮闘を見せ、伏見城は10日以上も持ち堪えたのですから驚きです。
元忠は最後まで戦うも、乱闘中に現れた鈴木重朝に敗れ、彼の介錯により自刀しました。
享年62歳、壮絶な最期を遂げた戦国武将「鳥居元忠」は、亡くなるまで家康に尽くした忠義者なのです。
死を覚悟で敵陣に突撃した赤鬼:山県昌景(やまがた まさかげ)
山県昌景は、武田家の家巨として戦国時代を生き抜き、華々しい人生を送った武将の1人。
1552年、武田信玄の信濃侵攻で勝利し、神之峰城攻めで侍大将に任命されました。
1565年には信玄の婿男でもある義信の謀反計画が公になりますが、昌景は信玄に忠告し阻止します。
家族の死をきっかけに山県姓を名乗り、昌景は兄の家臣団を指揮するようになりました。
後に武田家の、あらゆる武具を赤色にした軍団「赤備え」として、最強を誇る戦国軍勢と称賛されます。
1573年、信玄の死後、武田家の勢力は衰え、昌景は長篠の戦いで討ち死にしました。
徳川連合軍との戦いに敗れ、人生の幕を閉じたのです。
73歳にして撤退戦の要に:鬼庭左月(おににわ さげつ)
老齢にもかかわらず、軍の最後尾を固める部隊「殿(しんがり)」を務めたことで知られる鬼庭左月。
1586年、常睦の佐竹氏は、当時「独眼竜」の異名で知られる伊達政宗に戦いを挑みました。
初めは互角の戦いでしたが、軍の数から伊達軍に勝ち目はなく、押されていきます。
この時、殿に名乗り出たのが鬼庭左月でした。
当時左月が高齢であることから、殿を務めるのは難しいのでは…?と誰もが思ったそう。
しかし、この場所を自分の死に場所だと決意した左月は、周囲の言葉を聞き入れません。
左月は鬼神のような働きを見せ、相手に18度も突撃し、凄まじい奮闘を見せたといいます。
19度目の突撃で左月は討ち取られ、73歳で人生の終わりを迎えました。
病に抗うも切腹を余儀なくされた智将:大谷吉継(おおたに よしつぐ)
壮絶な最期を遂げた戦国武将として名が残る大谷吉継。
ハンセン病を患いながらも戦場で指揮を執り、最後は自死でこの世を去った戦国武将です。
吉継は豊臣秀吉の家巨で、敦賀城の城主を務めました。
1600年に始まった関ヶ原の戦いにも参戦。
昔から仲の良かった石田三成のことを思い、三成のいる軍に加わりました。
全力で戦いに挑むも、吉継は味方に裏切られて敗戦し、最後は自らの手で命を絶ちます。
吉継は友情を大事にし、最後まで戦い抜く姿は凄まじいものでした。
26歳にして腸をかき出し投げ捨て散った漢:仁科盛信(にしな もりのぶ)
仁科盛信は、武田信玄の5男として誕生しました。
織田・徳川軍から最大の強敵とされていた武田軍ですが、親類衆だった穴山信君や木曽義昌に裏切られ、勢力が衰えます。
やがて、織田・徳川軍は信玄がいる甲斐を目指して襲撃を開始。
織田軍の進路上にある城からは、次々と兵が逃げ出すなか、立ちはだかったのが高遠城でした。
高遠城にいた盛信は、織田軍を食い止めようとしていましたが、敵の軍が5万人に対し、武田軍は500人ほど。
少ない人数ながらも立ち向かいますが、半日もせずに城内への侵入を許してしまいます。
最期を悟った盛信は、自ら腹を十文字に斬り、腸をかき出して投げ捨てたそう。
26歳の若さで壮絶な最期を遂げた戦国武将の1人、仁科盛信はこうして短い生涯を終えたのです。
自ら殿となって槍を振るった鬼神:内藤昌豊(ないとう まさとよ)
武田四天王の1人として活躍した戦国武将「内藤昌豊」。
1573年、武田信玄の死後、後継者となったのが武田勝頼でした。
1575年になると、武田軍は1万5,000人を引き連れて長篠城を囲みます。
敵は500人ほどでしたが、敵は援軍要請を出し、3万8,000人にまで膨れ上がりました。
勝ち目がない武田軍は戦いを避けることを進言するも、勝頼は認めません。
しかし、敵の人数が圧倒的に多いことから、武田軍は崩壊の時を迎えます。
この時、本隊を逃がすために殿となったのが昌豊でした。
次々と味方が倒れるなか、昌豊は奮戦しましたが、とんできた矢が急所に命中。
それでも戦おうとする昌豊でしたが、敵に討ち取られ、人生の幕を閉じたのです。
なりふり構わず戦場に駆け出した鬼武蔵:森長可(もり ながよし)
織田信長に仕えていた森長可は、槍の名手として知られていました。
初陣は長可が15歳の時、味方に何もいわず1人で敵陣に乗り込み、27人もの首を取るという武功を挙げています。
1584年、小牧・長久手の戦いで徳川軍の奇襲を受けた長可は、眉間に銃弾を受けて戦死。
27歳という若さでした。
生前、凶暴さと冷酷さが味方にも恐れられていたとされ、味方の秀吉ですら長可の死に安堵したというエピソードが残っています。