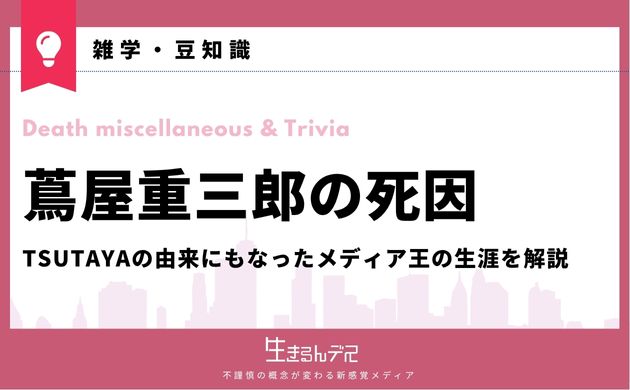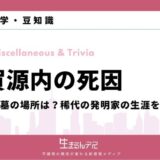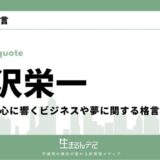みなさんは、江戸時代の出版業界をけん引した、蔦屋重三郎をご存じでしょうか?
彼は、本や映像作品の販売・レンタルなどを行うTSUTAYA(蔦屋書店)の由来になった人物です。
彼は当時、多くの文化人を世に送り出し、版元として江戸の文化を花開かせました。
今回は、彼の波乱万丈な生涯についてみていきましょう。
蔦屋重三郎の死因や最期は?
1774年の初刊行以来、多くの浮世絵師や作家に携わってきた蔦屋重三郎ですが、1797年に享年48歳でその生涯の幕を閉じました。
死因は、ビタミンB1不足による末梢神経の障害と、足がむくんだりしびれたりする病気「脚気」。
当時は「江戸わずらい」と呼ばれ、ビタミンB1が含まれる糠部分を取り除いた白米が主流だったことが原因とされています。
しかし、最期についてはほとんど記録に残っていません。
蔦屋重三郎の人生は?
多くの文化人を見出し、数々の作品を世に送り出してきた蔦屋重三郎。
版元として、まさに江戸のメディア王と呼ばれるにふさわしい生涯でしたが、どのような人生を歩んできたのでしょうか。
ここでは、彼の人生を振り返ります。
| 生誕 | 寛延3年1月7日(1750年2月13日) |
| 命日 | 寛政9年5月6日(1797年5月31日) |
| 享年 | 47歳 |
| 戒名 | 幽玄院義山日盛信士 |
生まれてすぐに吉原に養子に出される
蔦屋重三郎は1750年、遊郭の街・新吉原(現在の東京都台東区千束)で、尾張出身の父・丸山重助と、江戸出身の母・津与の間に生まれました。
本名は柯理(からまる)といい、7歳の時に引手茶屋を営む喜多川氏に引き取られ、本姓を喜多川とします。
よく知られている「蔦屋」は喜多川氏の屋号で、彼はここで幼少期を過ごしました。
田沼の政策を味方に書店として独立
重三郎が独立したのは1777年、彼が27歳の時です。
もともと、24歳から引手茶屋の軒先を間借りし、実質の1号店「書肆耕書堂」をオープンしていた重三郎は、ここで吉原遊郭のガイドブック「吉原細見」を編集し刊行。
もともとは鱗形屋と山本という2つの版元が刊行していましたが、山本が手を引いたため、版権を譲られた重三郎が代わりに手掛けたのです。
そして、1777年に書店として独立しますが、追い風になったのは当時の老中・田沼意次が、商業を重んじた貨幣経済中心の政策を推し進めたからです。
これにより、歌舞伎・浮世絵・戯作などの江戸の文化が花開きました。
寛政の改革の打撃を受け謹慎&罰金処分
しかし、重三郎の華やかな出版業は、やがていばらの道へ。
将軍の死をきっかけに失脚した意次に代わり、老中となった松平定信は、1787年寛政の改革を断行します。
これにより、質素倹約が奨励され、娯楽は厳しく取り締まられるようになりました。
案の定、重三郎は刊行物を摘発され、財産の半分を徴収されてしまいます。
喜多川歌麿・東洲斎写楽の生みの親となる
罰金処分を受けた重三郎ですが、出版物の方向転換はあったものの版元事業は継続。
大衆の心を惹きつけるため「浮世絵師をプロデュースしよう!」と思い立ち、喜多川歌麿や東洲斎写楽を起用しました。
歌麿の大首絵を多く刊行し、写楽にいたっては1794年5月から翌2月までの間、なんと130枚以上もの浮世絵を出版。
重三郎は一躍、浮世絵ブームの火付け役となりました。
波乱万丈の人生!2025年NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主人公に
幼くして養子に出され、間借りしたスペースで貸本屋を営んでいた重三郎の人生は、まさに波乱万丈といえますね。
独立し一度は追い風が吹くものの、娯楽を取り締まられ、自身も処罰を受けるなど出版業は縮小。
プロデュースした歌麿とはいつしか疎遠になり、写楽も姿を消し、自身も病に伏すなど苦難の連続でした。
そんな重三郎の人生がNHK大河ドラマで描かれます。
日本の文学や芸術の礎を築いた彼の生涯を、ぜひ知ってください。
蔦屋重三郎のお墓はどこ?
蔦屋重三郎のお墓は現在、東京都台東区浅草にある正法寺にあります。
ただ、震災や戦災で実物は失われたため、今あるのは新しく建てられたものです。
石碑には「喜多川柯理墓碣銘」と「実母顕彰の碑文」と記され、手を合わせることができますよ。