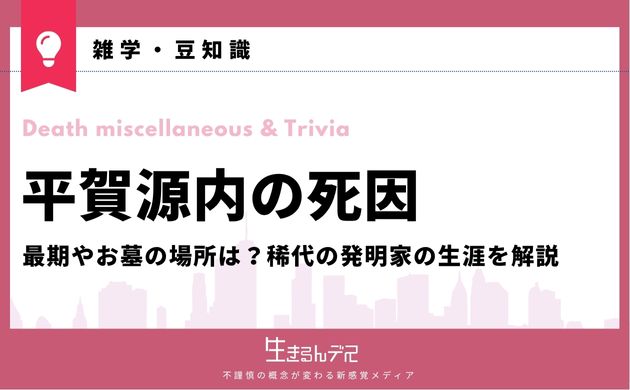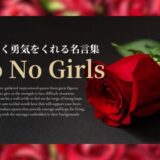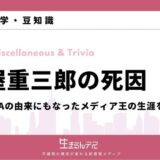日本には武将や文豪、歴史の改革に大きな影響を与えた人物などが偉人として歴史に刻まれています。
今回は、およそ260年続いた江戸時代に名を馳せた偉人の一人である「平賀源内(ひらがげんない)」について解説。
素晴らしい功績の一方で、自由人・破天荒といった異名もある彼がどのような人生を歩んでいたのか時系列順に紹介します。
平賀源内の死因や最期は?
平賀源内は51歳で生涯の幕を閉じました。
酔った勢いで人を殺めてしまった彼は、安永8年(1777年)に奉公所に自首をし、獄中で過ごすことになります。
獄中生活を開始してから1ヵ月後の安永8年12月18日に息を引き取るのですが、死因はおろか殺人の動機や、殺めた相手が誰だったのかも謎のままです。
そのため死因については、破傷風による病死や、自らを悔いて絶食したことによる餓死など様々な説がささやかれています。
平賀源内はどんな人生を歩んだ人物?
| 生誕 | 享保13年(1728年) |
| 命日 | 安永8年12月18日(1780年1月24日) |
| 享年 | 51~52歳 |
| 戒名 | 智見霊雄 |
享保13年(1728年)に高松藩(香川県高松市)の下級武士の元に生を受けた平賀源内は、幼少期より奇想天外なアイデアを考えつく少年として評判でした。
そんな彼の生み出したアイデアは当時の日本だけでなく、現代に生きる私たちの生活にも大きな影響を与えています。
そんな平賀源内がどんな人生を歩んできたのか、彼の生み出した数々の功績について解説します。
幼少期「おみき天神」にて奇才ぶりを発揮
白川家の三男として誕生した平賀源内には多数の兄弟がいましたが、好奇心の強さは中でも人一倍ありました。
幼少期には「天狗小僧」とあだ名がつけられるほど、いたずらが好きで周囲の人を困らせることも多かったようです。
12歳の頃には、お酒を供えられた掛け軸に描かれた天神様の顔がみるみる赤く染まる細工をして、周囲の人を驚かせています。
このからくりが施された掛け軸は「御神酒天神(おみきてんじん)」と呼ばれ大きな話題を集めました。
この評判がきっかけで、藩士の子らが学んでいた漢学や儒学のほかにも、13歳から藩医のもとで動植物や薬草を研究する学問・本草学を学ぶようになりました。
日本初の全国博覧会を開催
21歳のとき父の跡を継いで御蔵番の任務に就いた彼は、24歳になるとオランダとの貿易でヨーロッパの最先端の情報が集まっていた長崎へと遊学。
およそ1年間の遊学で、本草学・蘭学・油絵・医学などから世界の広さを実感した彼は、26歳に藩務退役願いを提出しクリエイター人生をスタートさせます。
一花咲かせようと江戸へと向かった源内は人脈を広げ、宝暦12年(1762年)には日本初となる「薬品会」を計5回開催。
全国各地の多種多様な物品を集めて展示し、日本における資源開発や活用について提案した全国博覧会は日本の発展にも大きな影響を与えました。
さらに、全国博覧会の成果をまとめた著書「物類品隲(ぶつるいしんしつ)」を1762年に発行。
本草学の実用性を重視した画期的なものとして大変価値のあるものとなりました。
何足のわらじ…?パラレルキャリアの先駆者
3度目となる全国博覧会を無事に終えた31歳のころに高松藩に呼び戻された彼は、薬草園を管理する任務を任されます。
しかし、藩での働き方に満足できなかった彼は33歳に二度めの藩務退役願いを提出し、幕府やほかの藩への仕官を禁ずる「仕官御構(おかまい)」という処置をとられました。
浪人として生きるしかなくなった彼ですが、持ち前の才気と構想力であらゆる分野で活動。
現代の小説のような「戯作(げさく)」や音楽劇「浄瑠璃」の台本を執筆しています。
ほかにも気温を測る「寒暖計」を制作したり、燃えにくい「火浣布(かかんぷ)」を開発したりと、多くの作品や発明を生み出しました。
また、現代でもお馴染みの「土用丑の日」という習慣は、平賀源内考案の宣伝により広まったと言われています。
エレキテルの復元に成功するも…
平賀源内を一躍有名にしたのが「エレキテル」という存在。
オランダから持ち込まれたエレキテルを復元し、摩擦で静電気を起こす機械として48歳のころに販売しました。
しかし、エレキテルの販売で得た利益は大きくなく、平賀源内の人生は決して順風満帆なものではありません。
さらには、エレキテルの復元が大きく評価される一方で、うさん臭い男という悪評も広がり周囲の目も次第に冷たくなっていきました。
本当に殺した…?謎の多い殺人事件で自首
エレキテルの復元から3年後の安永8年、平賀源内は人を殺傷したと奉公所へ自首しました。
有名人が起こした事件として江戸は大きな衝撃を受けたようです。
とある資料によると彼が殺傷した相手は大工とのこと。
平賀源内は大名屋敷の工事を請け負うことになり、大工たちと自宅で宴会を開いたようです。
しかし、お酒に酔った源内は設計図を大工に盗まれたと勘違いし、刀で斬ってしまったといわれています。
この説が有力視されているものの、異なる資料が残っていることから真相は分かっていません。
平賀源内のお墓はどこ?
獄中で命を引き取った平賀源内は、当時東京都台東区にあった総泉寺に葬られたとされています。
後に総泉寺は関東大震災で被災した折に板橋区小豆沢へ移転されましたが、彼のお墓は総泉寺跡地にそのまま保存することとなりました。
昭和6年に旧高松藩当主・松平頼壽により築地塀が整備され、昭和18年に国の史跡に指定され現在も「平賀源内墓」として残されています。
決して順風満帆とはいえない人生ではありましたが、平賀源内が生み出した物たちは現代文化の発展に大きく貢献しています。
殺人という許されない罪を犯してしまった彼ですが、国や人の利益となる大変な偉業を成し遂げた人物でもあるのです。