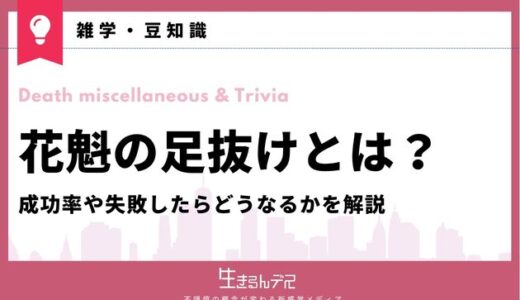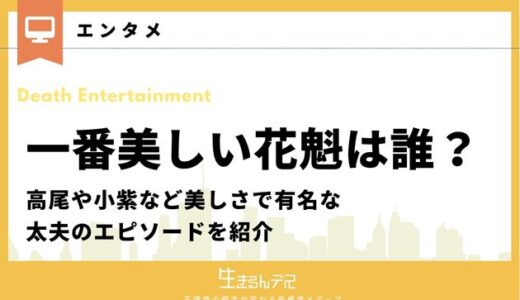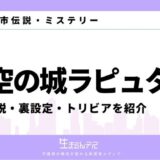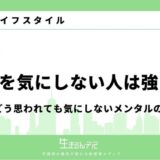吉原遊郭の遊女たちは、美しさや芸の技量、家柄などにより「ランク別の階級」がありました。
花魁と呼ばれた太夫(たゆう)など、遊女は階級によって着る物や待遇、吉原内での立場などに大きな格差があったのです。
この記事は、吉原の遊女の階級を紹介しています。
遊女の階級とは?吉原遊郭は階級社会?
遊郭は客と遊女が床を共にするだけでなく、プロのもてなしで宴席を楽しむ「社交の場」でもありました。
遊女には客のレベルに応じた美貌や家柄、芸事、教養が求められ、ランク別に階級が定められていました。
吉原遊郭には数千人の遊女がいましたが、階級により働き方や待遇、吉原での立場に格差があり、階級社会だったといえるでしょう。
トップクラスの花魁は、高価な着物や調度品を身につけ、浮世絵に描かれるなどスター的な存在でした。
遊女の階級|江戸時代中期まで
吉原遊郭の遊女の階級は、時代の流れによって変化するのも特徴の一つです。
江戸時代中期までは、裕福な武士や商人を相手にする「超ハイレベルの遊女」が属する階級もありました。
まずは、江戸時代中期までの遊女の階級を紹介します。
太夫(たゆう)
江戸中期までの吉原で、最高位の遊女の階級は「太夫」です。
太夫とは、歌舞伎など芸能で優れた人物に使われる敬称で、初期の遊女が舞台で歌舞伎を披露していたことからできた呼び名です。
太夫は、抜群の容姿や楽器演奏などの他、大名クラスの武士も会話を楽しめるような、高い教養を身につけていました。
太夫の中には、大名の伊達綱宗に気に入られて自分と同じ重さの金で身請けされたといわれる「高尾太夫」のような、伝説に残る太夫も存在しました。
格子(こうし)
太夫の次にあたる遊女の階級が「格子」です。
太夫には及ばないものの、レベルの高い遊女で美しく高い教養を身につけていました。
格子の呼び名は、遊女と遊ぶための揚屋(あげや)と呼ばれる宿で、格子の中で着飾った遊女が並んで客を待っていたことから、つけられたものです。
江戸時代中期以降になると、多くの武家が財政難になり、太夫や格子と遊べるような上客が減ったため、太夫・格子は徐々にいなくなりました。
散茶(さんちゃ)
太夫や格子より気軽に遊べる遊女は「散茶」と呼ばれました。
散茶とは挽いて粉にしたお茶のことで、茶葉の入った袋を振らなくても入れられる手軽なお茶を、客をフラない遊女に例えた呼び名です。
太夫や格子は気位が高く、気に入らない客は相手にしないこともありました。
1657年に吉原が浅草に移転した際、幕府は非公認の茶屋で働いていた遊女を吉原遊郭に集めました。
その時に遊女が急速に増えたため「散茶」クラスの遊女ができたのです。
遊女の階級|江戸時代中期から
江戸時代中期以降は、武家の財政難によって客が減ったので、太夫や格子のように育成にお金がかかる遊女はいなくなりました。
そして散茶が最上級の遊女となり、さらに下の階級が増えていきました。
次は、江戸時代中期以降にできた遊女の階級を紹介します。
呼び出し(よびだし)
太夫や格子が消えた後、散茶から派生した階級の1つで、この時代における最上級の遊女を意味します。
花魁と呼ばれた呼び出しは、格子の中で客を待つことはせず、客から呼び出しを受けるだけの遊女であることから名付けられた階級です。
華やかに着飾った花魁は、妹分や見習いの遊女を従えて、客の案内役である引手茶屋まで迎えに行きました。
華麗な花魁が吉原を練り歩く「花魁道中」は、吉原の名物として江戸の人々の注目を集めたそうです。
昼三(ちゅうさん)
昼三とは、昼営業の揚屋に呼んでも三分(0.75両)もかかるほど、揚代(料金)が高い遊女であることからついた階級名です。
昼三も散茶から派生した階級の1つで、呼び出しの次にランクが高い上級の遊女として、花魁と呼ばれました。
格子の中で客を待つことはせず、客に呼ばれると他の遊女たちを従えながら吉原を練り歩く、豪華な花魁道中が許されていました。
しかし、格付けごとに連れて歩ける人数には制限があったそうです。
附廻(つけまわし)
附廻は将来の昼三候補となる「有望な若い遊女」に与えられた階級。
揚代は二分(0.5両)程度なので、遊女の中ではランクが上の方ですが、花魁と呼ばれていたかは諸説あります。
また、呼び出し・昼三とは違って、花魁道中が許されていなかったとも言われています。
附廻は時代の変化とともに、以下で説明する「座敷持」と同じ意味で使われるようになりました。
座敷持(ざしきもち)
時代の流れとともに、揚屋に出向かず雇い主である妓楼の部屋で客を取る庶民向けの遊女の階級ができました。
それが座敷持と呼ばれる階級であり「局(つぼね)」とも呼ばれていました。
彼女たちは自分が生活するための部屋の他に、接客するための座敷も与えられており、そこに客を迎え入れたのです。
座敷持は、花魁と遊ぶようなお金がなくても遊べる「手軽な遊女」の階級でした。
部屋持(へやもち)
部屋持も「局」に属する遊女の階級で、ランクは座敷持より下です。
生活するための部屋を与えられていましたが、接客用の座敷は与えられず、自分が暮らしている部屋で客を取りました。
座敷持・部屋持は、遊女の年齢や営業成績などによって、階級が変わることもあったそう。
吉原遊郭の遊女も、業績次第で待遇や役職が変わる、現代のサラリーマンのような待遇を受けていたのですね。
新造(しんぞう)
新造とは、遊女になる前の見習い中の階級で、ランクは部屋持ちの下です。
吉原に来た少女は13〜14歳くらいから新造になり、先輩の遊女から接客のノウハウなどを学びました。
その中でも優秀な新造は「振袖新造」と呼ばれ、花魁候補として厳しい教育を受けたり、花魁道中に参加したりするなど、特別待遇でした。
しかし、新造は見込みがないと判断されると客を取らされるようになるので、遊女になる前から階級による格差がありました。
切見世(きりみせ)
切見世は、遊女の中で最もランクが下の階級で、間口の狭い部屋が連なった、粗末な長屋のような場所で客を取っていました。
「切」とは時間の単位を意味し、切見世は短い時間で客の相手をする遊女の階級です。
切見世の中でも揚代の金額によって階級があり、一番下の階級は揚代が2朱なので「二朱女郎」とも呼ばれました。
遊女以外のお仕事
吉原遊郭で働いていた人は、遊女だけではありません。
遊女の他にも、次のような人たちが吉原を支えていました。
禿(かむろ)
禿は新造になる前の、7〜13歳くらいの幼い少女で、遊女の身の回りの世話や雑用をしながら、歩き方・仕草などを学び、遊女となるための修行をしました。
禿や新造の衣装など、一人前の遊女になるまでにかかる費用は、花魁が負担していたそうです。
花魁(おいらん)の呼び名は、禿が付いている花魁のことを「おいらの太夫でありんす」と言ったのが、元になったと言われています。
遣手(やりて)
現代でも「遣手ババア」といった言葉が残る遣手は、遊女や新造、禿を監督する係の女性です。
吉原の妓楼には、どこでも必ず遣手がいました。
遣手は、遊女の働きぶりや生活態度を厳しく見張ったり、特定の客と恋愛をすると仲を引き裂いたりする役目があり、遊女にとって怖い存在でした。
遣手の仕事には、客の品定めや遊女の仲介、値段交渉なども含まれ、元は遊女だった年配の女性が遣手になることが多かったようです。
楼主(ろうしゅ)
楼主は、遊女が所属する妓楼の主人です。
貧しい家庭から借金のカタとして集めた少女たちを、遊女として働かせて大金を稼いだ楼主は「亡八(ぼうはち)」とも呼ばれました。
亡八とは、人として忘れてはならない「仁義礼智忠信孝悌」の8つの心を忘れてしまった、モラルが低い人間を軽蔑したあだ名です。
遊女に階級をつけて差別化したのも、吉原遊郭に注目を集めてより多くの客が遊びに来るようにするための、楼主の企みだったのかもしれません。
【遊女の気になるギモンを知りたいならこの記事から!】