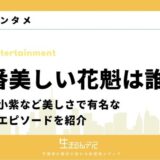現代ほど生理への理解がなかった江戸時代、遊女たちはどのように対処していたのでしょうか?
本記事では、閉鎖された環境の中で生理を迎えながらも仕事を続ける遊女たちの事情や、その対処法について詳しく解説します。
遊女は生理の時どうしていた?
江戸時代の遊女たちは、限られた環境の中で生理を迎えながらも仕事を続ける必要がありました。
現代とは異なる対処法や社会的な捉え方もあったため、その実態を詳しく見ていきましょう。
原則生理休暇は取れなかった
遊郭では、生理期間中であっても休むことは許されませんでした。
遊女は借金を抱えていることが多く、一日でも休めば収入が減り負担も増えるためです。
また、遊郭側も利益を優先していたため、生理による休暇を認めることはほぼありませんでした。
花魁は「身上がり」で休んでいた
一般の遊女は休むことが難しかった一方で、位の高い花魁は「身上がり(みあがり)」と呼ばれる方法で生理期間中に休めました。
これは遊女が「旦那」と呼ばれる特定の客を持ち、彼の庇護を受けることで特権的に休暇を取れる制度です。
しかし、このような待遇を受けられるのはごく一部の高級遊女に限られていました。
生理中の女性と交われば性病が治るという噂で命がけの業務に
江戸時代には、「生理中の女性と交われば性病が治る」という迷信が広まっていました。
この迷信を信じた客が遊郭に訪れ、生理中の遊女に対して性交を求めることもあったのです。
これにより、遊女は生理中でも客を取らざるを得ず、心身ともに大きな負担を強いられていました。
さらに、このような行為が性病の蔓延を助長する要因になったと考えられています。
生理中の遊女に使われていた隠語「行水」
遊女たちの間では、生理中であることを直接言うのははばかられたため、「行水(ぎょうずい)」という隠語が使われていました。
これは、川や風呂で体を洗うことを意味し「行水中」と言えば「生理中」であることを婉曲に伝える表現です。
このように、遊郭では公には言えないことも、隠語を使うことで暗に伝える文化が根付いていました。
江戸時代の生理への対処法
現代のような生理用品がない時代、彼女たちはどのように対処していたのでしょうか。
ここでは、生理期間中の対処法について見ていきましょう。
御簾紙(みすがみ)をふんどしで固定
当時の女性たちは、生理の際に「御簾紙(みすがみ)」と呼ばれる和紙を使用していました。
これは吸収性のある紙をふんどしのように布で固定し、現代のナプキンのような役割を果たしたものです。
しかし、吸収量が限られており頻繁に交換する必要があったため、遊女にとっては不便なものでした。
月経小屋へ隔離
一般の町民女性の中には、生理期間中に「月経小屋」と呼ばれる場所に隔離される風習もありました。
これは「血は穢れである」という考えからくるもので、とくに農村部では生理中の女性が共同生活の場から離れることが一般的だったのです。
ただし、遊女にはこうした隔離の風習はほぼなく、むしろ仕事を続けることを強いられていました。