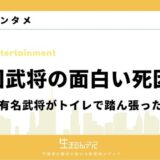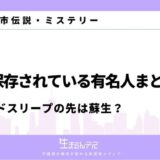江戸時代に遊郭で働いていた花魁。
時代劇やドラマで見たことはあるけれど、どんなことをしているか知っている人は少ないのではないでしょうか?
この記事では花魁とは何をする職業なのか詳しく解説していきます。
花魁とは何をする人?階級別に解説
江戸時代の遊郭には、さまざまな階級の遊女がいました。
とくに「花魁」は高位の遊女でしたが、その中でも「太夫」「格子」「散茶」などの階級があり、役割や待遇が異なっていたのです。
ここでは、それぞれの特徴を解説します。
太夫(だゆう)
太夫は遊女の最高位に位置し教養や芸事に優れ、歌舞・和歌・書道などの技能を極め、宴席を華やかに彩る存在です。
誰もが会えるわけではなく、限られた客のみが接することを許されていました。
また、十二単を思わせる豪華な衣装を身にまとい、特別な髪型を結っていたのも特徴です。
吉原内を移動する際には「道中」と呼ばれる儀式が行われ、禿(かむろ)や振袖新造(ふりそでしんぞう)を従え、格式の高さを示していました。
格子(こうし)
格子は太夫に次ぐ高級遊女で、裕福な客を相手にしていました。
太夫ほどの格式は求められないものの、礼儀作法や芸事に通じ、客との関係を築く社交性や会話術が重要視されたのです。
厳格な身分制度には縛られず、比較的自由に客を取ることができましたが、競争は激しく売れなければ下位の階級に落ちることもありました。
衣装は華やかさを保ちつつも動きやすさが重視され、遊郭内では「準高級遊女」とされていました。
散茶(さんちゃ)
散茶は遊郭内で最も低い階級に属する、庶民向けの遊女でした。
太夫や格子と比べると待遇が悪く、質素な衣装を身に着けているうえ特定の客を持つことは難しく、短時間で多くの客を相手にすることが求められていたのです。
また散茶が働く環境は劣悪で、吉原の端に位置する古びた店で仕事をすることが多かったとされています。
主な客層は労働者階級で、高額な遊びをする余裕のない庶民が中心ですが、美貌や才能が認められた散茶は、格子や太夫へ昇格することもありました。
花魁とは何をする人?花魁道中って何?
花魁とは、江戸時代の遊郭において最高位の遊女たちを指します。
単なる遊女とは異なり、高い教養と芸事を身につけ、上流階級の客をもてなす役割を担っていました。
彼女たちは厳しい修行を経て一流の話術や舞踊、書道などを習得したうえで客を取っていました。
花魁道中とは、花魁が客のもとへ向かう際に行われる豪華な行列のことを指します。
吉原などの遊郭では、花魁は付き人を伴いながら「外八文字」と呼ばれる独特な歩き方で優雅に進みました。
この道中は一種の見世物として、町の人々の注目を集める華やかな儀式でもあったのです。
花魁以外にも何をするかわからない遊郭内の職業
遊郭といえば花魁が有名ですが、実は遊郭内には多くの職業が存在していました。
これらの職業は遊郭を支える重要な役割を担っており、花魁だけでなくさまざまな人々が関わることで成り立っていたのです。
ここでは、遊郭内で働く「禿(かむろ)」「遣手(やりて)」「芸者(げいしゃ)」について詳しく解説します。
禿(かむろ)
禿(かむろ)は、太夫や花魁の付き人として仕える幼い少女たちを指します。
彼女たちは10歳前後で遊郭に入り、将来の遊女として修行を積みながら、先輩遊女の身の回りの世話をしました。
主な役割は、花魁の道中で付き添ったり、客の接待の補助をすることです。
まだ遊女としての仕事はできませんが、礼儀作法や芸事を学びながら成長し、適性が認められれば格子や太夫へと昇進する道もありました。
遣手(やりて)
遣手(やりて)は、遊郭内で遊女たちを管理する役割を担う女性たちです。
彼女たちは遊女のスケジュールを調整し、客の対応を監督するなど、裏方の重要な仕事を担当していました。
また、新しく遊郭に入った少女たちの教育も担当し、遊女としての作法や心得を教えました。
遣手は実務的な仕事をこなしながらも、遊郭の秩序を維持するために欠かせない存在だったのです。
芸者(げいしゃ)
芸者は遊女とは異なり、客との関係は芸事を通じたものに止まる存在です。
彼女たちは舞踊・三味線・詩歌などの芸能に精通し、宴席を華やかにする役割を担っていました。
接客が中心であるため、直接的な体の関係を持つことはなく、純粋に芸事を楽しませることが目的とされていたのです。
そのため、芸者の存在は遊郭の文化的な側面を支える重要な役割を果たしていたと言われています。