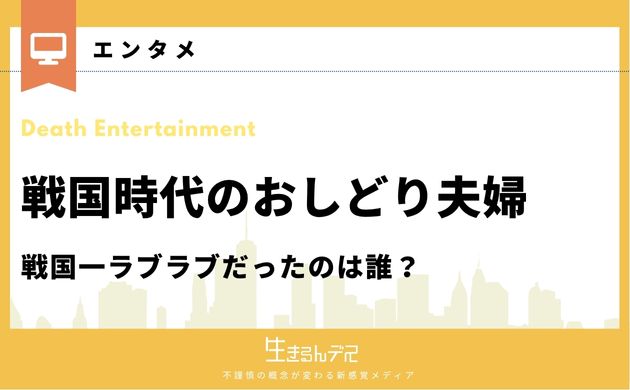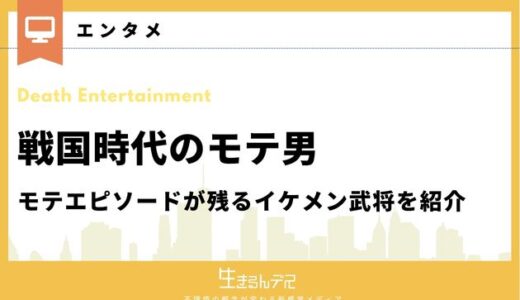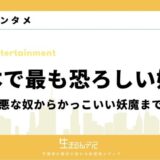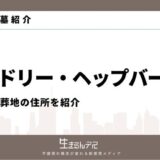各地で領土の奪い合いが起き、戦国大名の力が強まっていた戦乱の時代。
しかし、そんな中でもお互いを想い続け、おしどり夫婦と呼ばれたラブラブ夫婦が何組もいたのをご存じでしょうか?
今回は、史実を交えながら、さまざまな夫婦のエピソードについて解説します。
戦国時代のおしどり夫婦は誰?ラブラブな10組を紹介
毛利元就・妙玖
まずは、巧みな戦略と人徳で中国地方を統一した武将、毛利元就についてです。
元就には、妙玖(みょうきゅう)という妻がいました。
政略結婚にもかかわらず、2人はとにかく仲が良く、惚気とも思える手紙を息子たちに送るほどです。
実際、妙玖を妻に迎えてからは側室をもたず、妻が亡くなったときはショックで「隠居するんだ…」と言い出すほどの愛妻家っぷりだった元就。
その後も、子どもたちに送った手紙には、妙玖のことばかり書かれていたそうです。
明智光秀・熙子
つづいては、本能寺の変でお馴染みの裏切り者、明智光秀です。
光秀には、政略結婚によって結ばれた熙子(ひろこ)という正室がいました。
史料はほとんど残っていませんが、とても美人で心が清らかな女性だったことがわかっています。
実は、熙子との結婚の決め手となったエピソードがあるのです。
当時、流行り病の天然痘に感染していた熙子。
命に別状はないものの左頬に跡が残ってしまいます。
「こんな顔では…」と恥じた熙子は、自分ではなく妹を明智家に嫁がせようと両親に提案。
しかし、そんな熙子に対して光秀はある言葉をかけました。
「人の容姿は変わるけれど、心は美しいまま変わらない」と言ったのです。
熙子はこの言葉で結婚を決意し、光秀も愛妻家といわれるようになりました。
細川忠興・ガラシャ
武将でありながら文化人としても知られる細川忠興(ただおき)。
忠興は16歳のとき、信長の命で明智光秀の三女・ガラシャ(旧名・玉)と結婚します。
2人の関係性はほかの夫婦とは違い、危険で偏愛的なものでした。
とくに、忠興からガラシャへの愛はすさまじく、庭師がガラシャに見惚れていたという理由だけで首を斬り落とすほど。
しかし、ガラシャは怖がるどころか、何事もなかったかのように食事を続けたそうです。
忠興が、自分(ガラシャ)の着物で血のついた刀を拭ってもどこ吹く風。
そう、忠興は嫉妬深く、ガラシャはとても冷たい、火と氷のような温度差のある夫婦だったのです。
しかし、忠興の愛はどんなときも不変でした。
2年間別居しても、ガラシャがキリシタンになっても愛し続けました。
「キリシタンをやめろ!」「洗礼を受けるな!」と怒鳴ったり、ガラシャの行動を監視したりしますが、すべては妻を愛するがゆえのこと。
一方のガラシャも、棄教を迫られうんざりして離婚を決意しますが、屋敷や自分たちに危険が迫った際は、夫の言葉を守り潔く自害したそうです。
黒田孝高・光
次は、卓越した戦略眼と人徳に優れた軍師、黒田孝高こと官兵衛です。
官兵衛の妻は、播磨国の城主・櫛橋伊定の娘であった、櫛橋光(くしはしみつ)という女性です。
美人で健康、さらに才能もあったといわれ、現代でいう才色兼備な奥さんでした。
光のすごいところは、戦乱の世をくぐりぬける強さと官兵衛への深い愛情です。
夫が窮地に立たされたときは、家臣たちをまとめ家を守りました。
夫が病に倒れた際は、家督相続問題を冷静に進め、つつがなく長男を後継者にするほど。
そして、晩年は仏教に帰依し、官兵衛との信頼関係が揺らぐことはありませんでした。
前田利家・まつ
つづいては、加賀藩の祖であり豊臣秀吉の天下統一に貢献した武将、前田利家について。
利家の妻は、生後すぐに父を亡くし、利家の父の妻に引き取られた、まつ。
父の妻・竹野氏が利家の母の妹だったため、従兄妹にあたります。
そんな、まつと利家は12歳と20歳のときに、この時代には珍しい恋愛結婚をしました。
子宝に恵まれ、絵に描いたようなおしどり夫婦だったそうです。
まつのすごいところは、夫・利家に厚い信頼を寄せているところでしょう。
信長にお払い箱を言い渡されたときは、なんと2年も利家の復帰を待っていたまつ。
夫の死後、息子に謀反の疑いがかかった際は自身が人質になるなど、夫の生前・死後にかかわらず前田家を支え続けました。
浅井長政・市
次は当時、北近江(現在の滋賀県北部)を支配していた武将、浅井長政(あざいながまさ)。
長政の妻は、織田信長の妹であるお市の方。
同盟関係を結ぶための結婚でしたが、2人の仲はとても良く、茶々(のちの淀殿)・初・江の三姉妹をもうけるなど、誰もがうらやむ華やかな人生を送ったそうです。
しかし、その一方で2人は悲劇的な最期を迎えます。
長政が、かねてより盟友関係にあった朝倉家と信長が交戦することになったのです。
同盟関係は崩れ長政は信長と刃を交えますが、応戦虚しく浅井軍は滅び、長政は小谷城(現在の滋賀県長浜市)で自害。
やがて、4人は織田家に引き取られますが、お市の方は秀吉に興味を持たれたり、柴田勝家と再婚したりと、数奇な運命を辿っていきます。
そして、豊臣軍に追い詰められた勝家とお市の方はともに自害し生涯を終えました。
吉川元春・新庄局
謀略の神と呼ばれた毛利元就の次男、吉川元春(きっかわもとはる)もおしどり夫婦として有名です。
元春の妻は、家臣である熊谷信直の娘・新庄局。
彼女は、容姿があまりよくないため、信直は嫁ぎ先がないと嘆いていました。
そんな信直の姿を見た元春は、自分が娘と結婚すれば信直が喜び、今後も毛利家のために尽くしてくれるだろうと考え、新庄局を妻にします。
実際、信直はより一層毛利家に尽くし、新庄局も陰ながら夫と家を一生懸命支えました。
元春のすごいところは、やや邪な目的で結婚したにもかかわらず、新庄局を生涯愛し続けたこと。
側室は一切娶らず、新庄局だけに愛情を注いだ愛妻家なのです。
前田利長・永姫
加賀藩の祖・前田利家の息子である前田利長もおしどり夫婦でした。
利長の妻は、まだ幼い頃に利長と婚約した、織田信長の娘のひとり永姫(えいひめ)。
信長の娘ということもあって、永姫は利長とともに激動の時代を生き抜いてきました。
実際、2人は信長のもとに向かう途中、本能寺で信長が討たれたことを耳にし、引き返したという逸話が残っています。
そして、利長は生涯、妻である永姫以外娶らなかったそうです。
ただ、後継者となる男子には恵まれず、前田利常を養子に迎え家督相続させたといわれています。
豊臣秀吉・ねね(おね)
農民出身でありながら数々の武勲を挙げ、天下人と称される武将、豊臣秀吉。
秀吉の妻は、尾張国朝日村(現在の愛知県清須市)で農家をしていた、杉原定利と朝日殿の次女・ねね。
当時、信長の家臣で、まだ身分の低かった秀吉と出会い、恋愛の末ゴールインしました。
母に結婚を反対されたり、子どもに恵まれなかったりと大変な思いをしたねねですが、秀吉を献身的に支えます。
実際、秀吉はねねの手腕を信頼し、家や政治などについて相談するほどだったそうです。
お互いに強く結ばれていたため、ねねは秀吉の死後も関白として豊臣家を支えました。
今川氏真・早川殿
最後は、桶狭間の戦いで織田信長に討ち取られた今川義元の息子、今川氏真(うじざね)についてです。
氏真の妻は、相模国小田原(現在の神奈川県)の戦国大名であった北条氏康の娘・早川殿。
彼女は、武田・北条・今川氏の間で結ばれた同盟の婚姻政策のひとつとして、氏真に嫁ぎました。
聡明だった早川殿は、ほかの戦国武将の妻と同じく、氏真・家臣・家・領民までも支え、内助の功を尽くすほど。
夫が亡くなったあとは、江戸で余生を過ごしたといわれています。
【戦国武将に関連する記事はこちら!】