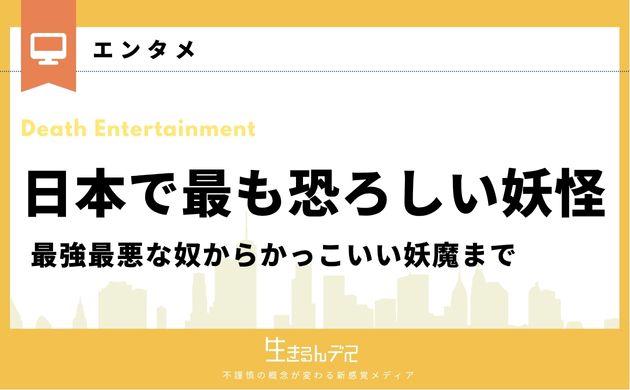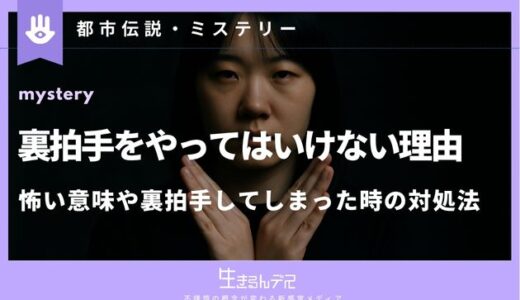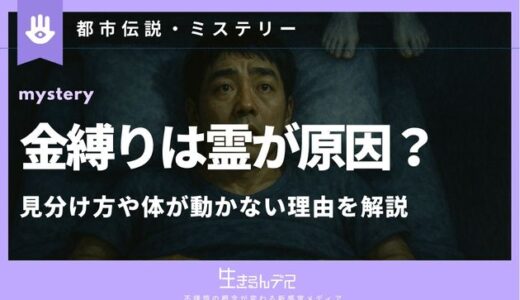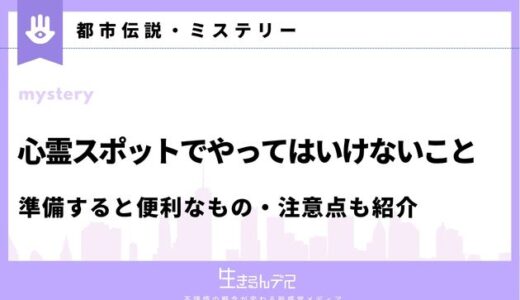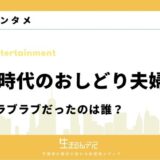多くの人を魅了し、恐れさせた妖怪。
現在、日本には1500種類以上の妖怪が存在し、恐怖とユーモラスを混じえた日本文化として残り続けています。
この記事では、日本で最も恐ろしい妖怪を厳選して10体紹介!
歴史的な背景とともに、妖異の魅力や恐ろしさを紐解いていきましょう。
第10位|青頭巾(あおずきん)
青頭巾(あおずきん)は、江戸時代後期の作家、上田秋成が書いた小説「雨月物語」の中にある作品の1つ。
愛してやまない稚児を病気で亡くした僧侶は、悲しみのあまり人の心を失い鬼となり、村人を襲う、恐ろしいストーリーです。
最後は高僧、快庵禅師が僧侶に青頭巾を被せて成仏します。
人間の業深さが描かれた青頭巾は今もなお、人々の記憶に強く残っているでしょう。
第9位|猫又(ねこまた)
日本の民謡や怪談に登場する猫又(ねこまた)。
「飼い猫が妖怪になった」「山猫が化けたもの」という、2種類の物語が存在します。
地域によって描かれ方が異なりますが、共通しているのは尻尾が2つにわかれていること。
長生きした猫が化けるといわれており、日本にとどまらず、中国でも不気味な伝承として残り続けています。
第8位|絡新婦(じょろうぐも)
江戸時代の怪談集「太平百物語」や「宿直草(とのいぐさ)」などの書物に描かれている女郎蜘蛛(じょろうぐも)。
美しい姿をした女郎蜘蛛は、夜になると巨大な蜘蛛に姿を変えて人間を襲う恐ろしい妖怪です。
女郎蜘蛛が吐く青い煙は、やがて小さな蜘蛛となり、人々の生き血を吸い上げます。
絡新婦(じょろうぐも)は、土曜ナイト系ドラマ「妖怪シェアハウス」や、テレビアニメ「どろろ」にも登場しています。
日本で最も恐ろしい妖怪として名の知られた女郎蜘蛛は、人々の心を刺激する恐怖の象徴ともいえるでしょう。
第7位|河童(かっぱ)
河童(かっぱ)は川や池に住み、頭にお皿がのっている緑色の妖怪。
大好物はきゅうりで、お寿司屋さんのメニュー「かっぱ巻き」の由来にもなっています。
亀のような甲羅を背負い、背丈は人間でいうと3歳〜6歳児ほど。
かわいらしい河童ですが、人を川に引きずり込むという恐ろしい一面があります。
今でこそ愛くるしいキャラクターとして親しまれていますが、本来は人を溺死させる、イメージとは真逆の妖怪なのです。
第6位|天狗(てんぐ)
日本の伝説となっている最強最悪の妖怪「日本三大悪妖怪」の1人、天狗(てんぐ)。
真っ赤な顔や長い鼻が印象的な天狗は、高い神通力を持ち、火災を起こしたり、人をさらったりするなど、恐れられてきました。
しかし、江戸時代からは、神のような存在として天狗への認識が変わります。
火災を防ぐ力があるとして、静岡県の秋葉山に祭られる秋葉権現(あきはごんげん)は、火伏せの神として有名です。
第5位|鵺(ぬえ)
平家物語に登場する鵺は顔が猿、胴体は狸、手足は虎のような姿形をした、得体のしれない妖怪が鵺(ぬえ)です。
夜になると不気味な声で鳴いて不吉をもたらすといわれ、多くの人が不安な一夜を過ごしたとされます。
この状況に黙っていなかったのが源頼朝。
弓矢で鵺を射止め、平和な日常を取り戻したという話は有名です。
第4位|酒呑童子(しゅてんどうじ)
平安時代から知られている酒呑童子(しゅてんどうじ)は、神隠しをすることで知られる妖怪です。
お酒が好きなことから「酒呑童子」と呼ばれていることを知った家来は、泥酔させてその間に撃退しようと考えました。
お酒を振る舞い、楽しんだ後、寝床についた酒呑童子を襲い、退治したといわれています。
「人を襲って食べた稚児が成長した姿」「八岐大蛇の落とし子」などの説がありますが、最も恐ろしい妖怪として認知されていることはいうまでもありません。
第3位|玉藻前(たまものまえ)
平安時代に羽鳥上皇から愛されていた玉藻前(たまものまえ)は、美貌と物知りであることから慕われていました。
しかし、ある時、陰陽師は気づいてしまいます。
何を隠そう、玉藻前は九尾の狐であり、人間に扮して生活していたのです。
正体がバレた玉藻前は、九尾の狐になって逃げていきました。
人や動物の命を奪い、街中に恐怖を知らしめていましたが、栃木県で発見。
武士により退治されたという、伝説にもなった妖怪です。
第2位|祟徳天皇(すとくてんのう)
崇徳天皇(すとくてんのう)は3歳のころ、第75代の天皇として任命されました。
しかし、保元の乱で敗北し、讃岐国(香川県)へ流刑と遭います。
崇徳天皇は、反省や犠牲者の供養を込めて写本を書くものの、呪いがかかっていると疑われ、受け取ってもらえません。
腹を立てた崇徳天皇は舌を噛み切り、その血で「日本を滅ぼす大魔縁になる」と書き残しました。
その姿は「日本で最も恐ろしい妖怪」に相応しく、人間の理解を超えた凄まじい形相だったに違いありません。
第1位|八岐大蛇(やまたのおろち)
八俣大蛇(やまたのおろち)は「古事記(こじき)」に登場する妖怪。
須佐之男命(すさのおのみこと)は、出雲の阿国で櫛名田比売(くしなだひめ)という美しい女性に出会います。
しかし、姫は毎年娘を喰らう八岐大蛇に食べられてしまいそうでした。
そこで結婚を条件に退治を買って出た須佐之男命は、八俣大蛇にお酒を飲ませて酔わし、そのすきに8つの頭を切り離したのだとか。
その後、八俣大蛇から須佐之男命の剣が発見されています。
この剣が「草薙剣」として有名となり「日本で最も恐ろしい妖怪」として、恐怖と驚きを与えた逸話です。
【ホラーについてもっと知りたい人はこちら】