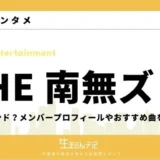平和な時代が続いていた江戸時代には、現代では想像もつかないようなおもしろい職業がたくさん存在しました。
この記事では、江戸時代に実在していた職業を15個紹介します。
江戸時代に実在した面白い&やばい職業15選
江戸時代に実在した職業は、実用的なものから信じられないものまで多数あります。
人々がどのような仕事で生計を立てていたのかを知り、江戸時代の空気を感じましょう。
屁負比丘尼(へおいびくに)

屁負比丘尼(へおいびくに)とは、身分が高い女性がした放屁の身代わりになる仕事です。
常に女性の傍らに寄り添って、女性が放屁をしたら「私がしました」と申告します。
身分が高い女性にとって、放屁はとても恥ずかしい行為なので絶対に「自分がした」とバレるわけにはいきません。
そのため、屁負比丘尼(へおいびくに)が身代わりとなって、その恥ずかしさを請け負っていました。
ちなみに、放屁の音を聞き逃さず、演技力に優れた若い女性が選ばれていたそうです。
耳の垢取り屋

「耳の垢取り」は、耳掃除をする仕事です。
神田紺屋町には耳の垢取り名人がいて、そこには遠方からも多くの人々が訪れたといわれています。
また、竹の耳かきが誕生したのも江戸時代とされているため、この頃の人々にとって、耳垢を取ることはとても重要だったのでしょう。
猫のノミ取り屋

「猫のノミ取り」は、名前の通り猫のノミを取る仕事です。
江戸時代はノミ駆除用の薬など無かったため、猫にたくさんのノミがたかっていました。
そのため、ノミ職人は猫を湯浴みさせた後、動物の毛皮で包んでノミが自ら毛皮に移動するようにします。
一見効率的な方法に見えますが、毛皮に移る確証などはありません。
そのため、ノミ取りのコツが広まるにつれて人気が無くなったともいわれています。
独り相撲

「独り相撲」とは、町中で独り相撲を取る大道芸です。
ただ相撲の真似をするのではなく、力士2人と行司を一人で真似します。
本格的な演技は、多くの人々が楽しめる人気パフォーマンスだったようです。
人気がある力士や行司のモノマネも取り入れていたことから、現代でいうモノマネ芸人に近いのかもしれませんね。
鋳掛屋(いかけや)

「鋳掛屋(いかけや)」とは、鍋などの調理器具に空いた穴やすり減った底を直す職業です。
江戸時代の調理器具はすべて手作りで、とても貴重なものでした。
高額だったため、一度買ったものを直しながら使うことが一般的だったのです。
そのため、鋳掛屋は町を回りながら、調理器具の修理で生計を立てていました。
親孝行

「親孝行」とは、老人を背中に背負って町を練り歩き「親孝行でござい」と周りにアピールする職業。
周囲の人々は、老いた親を背負って歩くその姿に感動し、小銭を渡していたそうです。
しかし「親孝行」の中にはハリボテ人形や、全く知らない赤の他人を背負って歩いている人もいたといわれています。
考えもの

「考えもの」とは、現代でいうパズルやクイズなどが書かれた紙を人の家に投げ込み、答えを教える代わりに銭をもらう職業です。
家主が紙を見て考え込んでいるときに「答えが気になるでしょう?」と声をかけて、銭と引き換えに答えを教えるのです。
娯楽の提供と考えれば、納得の職業ですね。
鳥の糞買い

「鳥の糞買い」は、美容に使われていた鳥の糞を集めて売る職業です。
この頃、江戸時代の町民は小鳥を飼育することが多く、その小鳥の糞を集めて周り、美容品の原材料として販売していました。
また、鳥の糞は着物の染み抜きにも使われていたそう。
鳥の糞を集める際に、鳥かごの掃除もしてもらえるため町人にとっても都合が良かったのでしょう。
御利生(ごりしょう)

「御利生(ごりしょう)」とは、鳥居のような枠組みを持って、その中から狐の首を伸び縮みさせるパフォーマンスをおこなう職業です。
「葛西金町半田の稲荷、御利生御利生大きな御利生、すてきな御利生」という口上でおこなわれたパフォーマンスは子供にも人気だったそう。
「御利生」とは神仏からもらう恩恵という意味ですが、この時代では男根の隠語として使われていました。
そう考えると、大人向けのパフォーマンスだったのかもしれませんね。
お万が飴

「お万が飴(おまんがあめ)」とは、女装をして飴を売る行商人です。
女性の格好をした彼らは、高い声を出し、歌や踊りで人々を引き付けました。
この仕事はとても評判が良く、歌舞伎舞踏の所作事で題材になるほど流行したといわれています。
唐人飴売り

「唐人飴売り(とうじんあめうり)」は、江戸後期から明治にかけて見られた職業です。
唐人空売りは、異国風の服装でチャルメラや踊りを使って人を集めていました。
ただし、売っていたのは棒状に引き伸ばした飴で、とくに海外の特別な品というわけではあ
りません。
賑やかで目立つ衣服やパフォーマンス込みの職業といえるでしょう。
小便仲間

「小便仲間」とは、人の尿を集めて売る職業です。
この頃、尿は肥料として使われていたため重要な資金源だったのです。
しかし、公衆便所や長屋の共用トイレなどは、管理者が尿を集めて売ってしまうため集められません。
そのため、小便仲間は町中の立ちションスポットに桶を置き、その桶に入った尿を集めて売ります。
縄張り争いがとても激しく、桶を動かしたり、他人の桶に水を薄めて品質を下げたりする工作もおこなわれていたそうですよ。
縁切り寺

「縁切り寺」は、夫婦が離婚をする際の仲介役をおこなう職業です。
江戸時代では、離婚するために離縁状を作らなければいけませんでした。
しかし、この離縁状は男性しか書けず、女性は自らの意思で離婚できなかったのです。
そのため、縁切寺は女性の訴えを聞き、男性に離縁状を書かせるという役割をになっていました。
ただし、女性側の言い分に不明点や疑問点がある場合は、家に帰されることもあったそうです。
イモリ売り

「イモリ売り」とは、惚れ薬として人気だったイモリを販売する職業です。
イモリは、番(つがい)になると決して離れないため「お互いにイモリの黒焼きの粉を振りかけると恋愛成就する」というジンクスが信じられていました。
そのため、イモリ売りからイモリを買い、意中の相手に使う人が多かったのです。
孫太郎虫売り(まごたろうむしうり)

「孫太郎虫売り(まごたろうむしうり)」とは、ヘビトンボ科の幼虫を売る職業です。
江戸時代の子供は、癇癪持ち、消化不良のような症状が多く、現代では「栄養失調だったのでは」と推測されています
しかし、その頃は「疳の病」「疳の虫」といわれていました。
その症状に効くとされていたのが、孫太郎虫です。
孫太郎虫売りは、疳の虫を患う子どもがいる家に虫を売って生計を立てていたのです。