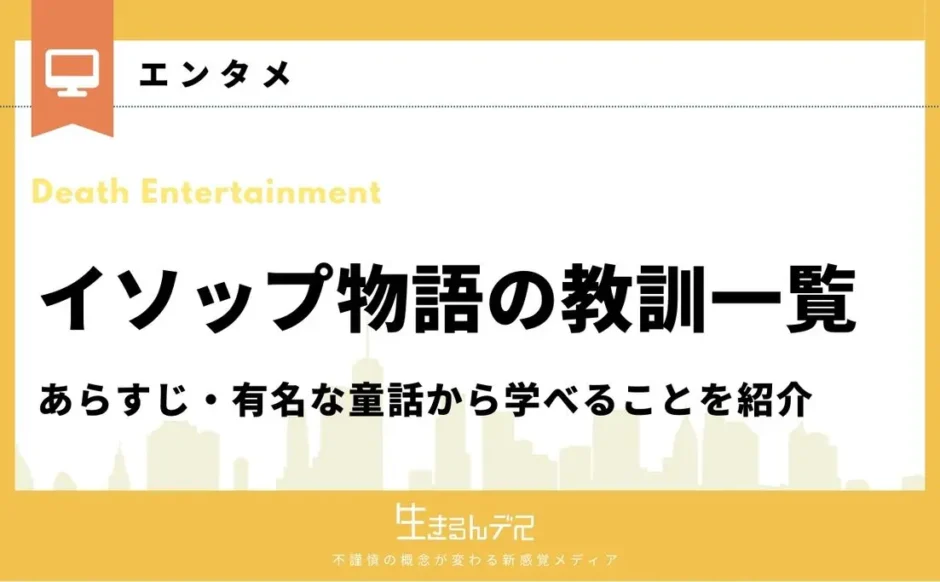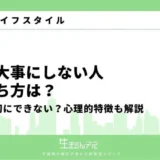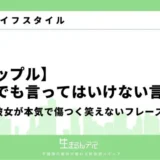古代ギリシアの寓話(ぐうわ)作家・イソップが描いたとされるイソップ物語(寓話)。
『ウサギとカメ』や『きんのおの』のように動物や金物、また自然や食べ物などを題材にしていることで有名です。
今回は、イソップ物語で学べることについて解説します。
イソップ物語の教訓とあらすじ一覧|有名な童話
まずは、いくつかの教訓とあらすじについてみていきましょう。
アリとキリギリス
まず『アリとキリギリス』から学べることは、先のことを考え計画的に行動することの大切さです。
ある夏、アリたちは厳しい冬に備え、食べ物を運び、あくせく働いていました。
一方、キリギリスは、大好きなヴァイオリンを弾き自分の好きなように過ごしています。
キリギリスはアリたちを見て「あんなに働いて何が楽しいのか」と思っていました。
しかし、いざ冬が到来すると、キリギリスは「食べ物がない…」と気づき、アリにもらいに行きます。
書籍によっては、ここで結末が2つに分岐します。
1つ目は、アリから食糧をもらいキリギリスが改心するというハッピーな終わり方。
2つ目は、バカにされたアリはキリギリスに食糧を与えず、餓死するというパターンです。
どちらの結末にせよ、娯楽にかまけていたら後で後悔することになります。
先を見通し、計画的に働くことが大切なのです。
ウサギとカメ
『ウサギとカメ』から得られる教訓は、自分の能力を過信しすぎるのはNGということです。
ある日、カメはウサギと競争することになりますが、自慢の脚力でどんどん突き放します。
のろのろと進むカメを見かねたウサギは「少し休憩するか」と思い、待っている途中で居眠り。
しかし、目を覚ましたときはすでに遅く、なんとカメはゴールしていたのです。
自分の能力を過信したウサギの負けでした。
何事も油断大敵、そしてコツコツ努力すれば必ず結実することが、このストーリーから学べます。
きんのおの
『きんのおの』における教訓は、嘘をついたら自分の大切なものを失うということです。
ある日、正直者の木こりは池に鉄の斧を落としてしまいます。
すると、現れたのは金と銀の斧を持った神様。
「どちらの斧か」と問われた木こりでしたが、どちらでもないと正直に答えます。
神様は木こりの正直さを褒め、3本とも与えました。
一方、これを聞きつけた別の木こりは、わざと斧を落とします。
思惑通り「金の斧です」と答えますが、神様はすべてお見通しです。
金の斧は与えず、彼が持っていた斧も池の底に沈みました。
強欲や嘘は、自分の大切なものまで失うことを学ばせてくれます。
北風と太陽
『北風と太陽』で学べることは、何事も力づくなのはよくないということです。
ある日、通りかかった旅人のコートを、どちらが先に脱がせるかの勝負をしていた北風と太陽。
ピューっと風を吹かせた北風ですが、旅人はぎゅっとコートをおさえ寒さに耐えます。
結局、いくら風を吹いても旅人のコートは脱がせられませんでした。
一方、太陽は旅人に光を当て続け、旅人は暑さからついにコートを脱ぎます。
勝者の太陽から得られるのは、何事も力づくではなく、ときにはゆっくり一歩ずつに進めることが大事という教訓です。
犬と肉
『犬と肉』から得られる教訓は、決して欲張ってはいけないということ。
ある日、欲張りな犬が肉を咥え橋を渡ろうとしていました。
すると、橋の下を流れる川(水面)に、同じく肉を咥えた一匹の犬が。
欲張りな犬は、相手の肉も自分のものにしようとワンワンと吠えます。
しかし、咥えていた肉が川に落ち、欲張りな犬は自分の姿が映っていただけだと気づきました。
あれもこれもと欲張らなければ成功していたという教訓です。
オオカミ少年
『オオカミ少年』における教訓は、嘘を重ねると誰も信用してくれなくなるということです。
退屈のあまり「狼が来るぞ!」と嘘をつき、何度も村人を騙していた一人の少年。
ある日、本当に狼が現れますが、村人たちは少年への信用を失っていたため助けに来ませんでした。
たとえ、悪気はなくても嘘を重ねれば、誰からも信頼されなくなります。
そして、いざとなったとき、手を差し伸べてもらうこともできません。
正直であることの大切さを教えてくれる物語です。
キツネとブドウ
『キツネとブドウ』における教訓は、自分の能力不足をしっかり受け入れることです。
一匹のキツネが、木になっているブドウを見つけて取ろうとします。
しかし、どうしても手が届きません。
すると、キツネは「あんな青臭いブドウなんて食べてやるものか!」と言って、去っていきました。
ここでの学びは、酸っぱそうだからといって言い訳してはいけないこと。
取れなかったのは自分の能力不足であって、ブドウのせいではありません。
悔しい思いをするのなら、どうすればよかったか行動を見直すことを諭してくれています。
ガチョウと黄金の卵
『ガチョウと黄金の卵』から学べることは、小さな幸せに感謝することです。
ある日、男は自分が飼っているガチョウが金の卵を産んでいることに気づき、それを売ろうと考えます。
予想通り、卵は高値で売れ、その後もガチョウは1日1個ずつ産み続けました。
しかし、たった1個ずつしか産まれないことにもどかしくなった男は、お腹の中に詰まっているのではと考え、なんとガチョウの腹を裂きます。
すると、お腹の中に金の卵はなく、ガチョウも死んでしまいました。
ここでの教訓は、日々の小さな幸せに感謝すること。
そして、欲深い者はやがて、今ある幸せを失うことを教えてくれています。
たとえ1個でも「毎日ありがとう」と感謝することが大切なのです。
ウマをうらやんだロバ
最後に『ウマをうらやんだロバ』で得られる教訓は、誰もが苦労していることを知るべきということです。
一頭のロバは、自分の隣で飼われている馬をうらやんでいました。
自分は質素な餌で、馬はおいしそうな餌をもらっていることに。
「馬だったらよかったのに」と、ロバは何度も思いました。
しかし、戦争がはじまり、戦地から傷だらけで帰ってきた馬は「ロバだったらよかったのに」と言います。
すると、ロバは「馬も苦労しているんだ…」と気づき、その後うらやむことはありませんでした。
自分だけが大変なのではなく、幸せに見えて実は誰もが苦労しているということを学ばせてくれるストーリーです。
イソップ物語とは?
いくつか教訓とあらすじを解説しましたが、そもそもイソップ物語とは、元奴隷のアイソーポスという作家が描いた寓話集。
主に動物のほか、食べ物や生活必需品などを主人公にし、数百篇が描かれたといわれています。
ただし、そのすべてがアイソーポスの作品ではなく、別人が伝えた寓話が、現代のイソップ物語として集約されているそうです。
イソップ物語における動物の描かれ方は?
イソップ物語には、ウサギ・カメ・ガチョウ・ロバなどのさまざまな動物が登場します。
特徴的なのは、彼らがまるで人間のように主人公になっていること。
現代の人間にも当てはまる価値観や性質を持っており、学びや風刺を利かせたストーリーになっています。
いくつかの動物の描かれ方をみていきましょう。
- ライオン:「権威」の象徴で、他の者から畏れ敬われる存在として描かれる
- キツネ:「狡猾さ」を象徴し、非常にずる賢い者として描かれる
- オオカミ:「残酷さ」のシンボルで、乱暴・横柄な性格として描かれる
- ロバ:「愚鈍さ」を表し、状況が把握できない愚かな存在として描かれる
このように、動物ごとに描かれ方が異なり、どれも人間性に通じるところがありますね。
動物を通して、人間のとある一面を見ているといえるかもしれません。
イソップ物語が日本に広まったのはいつ?
イソップ物語が日本に広まったのは、明治時代といわれています。
もともと、戦国時代にはすでにイエズス会の宣教師によってイソップ寓話が伝わっていました。
しかし、ラテン語・ドイツ語・フランス語・オランダ語などへの翻訳を経て、本格的に出版されたのは江戸時代初期のこと。
とはいえ、翻訳のせいか『伊曾保物語』の普及はまだまだでした。
ただ、明治時代には翻訳が進み、教科書に取り入れられるほどに。
子ども向けに翻訳されたのは戦後のことで、今では岩波文庫や小学館など、多数の出版社から発行されています。