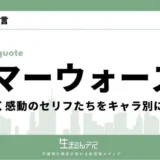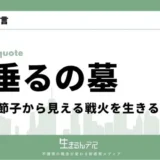「事故物件」と聞くと、不吉・怖い・トラブルが多そう…そんなイメージを抱く人も少なくないでしょう。
実際には、事故物件にも明確な定義や基準があり、全てがそういった物件というわけではありません。
この記事では、「事故物件とは?どこまでが告知義務なの?」という基本から、住む上でのデメリットやメリット、見分け方まで詳しく解説します。
事故物件とは?告知があるのはどこまで?
事故物件とは、建物や土地で前の住人が死亡した経歴がある物件のことを指します。
主に「殺人」「自殺」「自然死」などによって亡くなったケースが代表的です。
ただし、それらをすべて同じく“事故物件”と扱うかどうかは、実は非常に曖昧。
たとえば、家族と共に暮らす高齢者が亡くなりすぐ発見された場合は、一般的なケースとして扱われるため、告知義務の対象外になる場合もあります。
一方で、自殺や殺人事件があった場合には、次の入居者に「告知事項」として伝える義務があります。
事故物件はやめたほうがいい?デメリットを紹介
事故物件には安さや好立地といった魅力もありますが、注意しなければならない点も少なくありません。
見た目にはわからなくても、住んでから後悔するような精神的・物理的リスクが潜んでいるケースも。
ここでは、事故物件を選ぶ前に必ず知っておきたい、代表的なデメリットについて詳しく解説します。
精神的負担が大きい
事故物件の大きなデメリットは、心理的な不安を抱えながら生活することです。
自殺や他殺があった物件だと、何気ない生活の中でもその背景を思い出してしまい、ストレスや不眠を引き起こすことも。
特に、ひとり暮らしや夜間の静寂が苦手な人は、慎重な判断が必要です。
臭い・シミなど痕跡が残っている可能性がある
死亡後に発見が遅れた場合、遺体から出る体液や臭気が残ってしまうことがあります。
特殊清掃やリフォームが施されていたとしても、わずかに残る異臭やシミが気になることも。
それが結果として、体調不良や精神的なストレスの引き金になるケースも少なくありません。
怪異が発生するかもしれない
「誰もいないのに足音が聞こえる」「寝ていると気配を感じる」など、説明のつかない怪異に遭遇したという声も多くあります。
もちろん、すべてが心霊現象とは限らず、建物の構造や生活音が影響している場合もあるでしょう。
とはいえ、霊感がある人や敏感な人は、避けておいたほうが無難かもしれません。
いたずらやトラブルに巻き込まれやすい
有名な事故物件はネットで拡散されやすく、住所が特定されてしまうことも。
その結果、心霊マニアが勝手に訪れたり、郵便物を送りつけられるといったトラブルが発生する可能性があります。
特に、ニュースで取り上げられた物件はその傾向が強くなります。
近所の間で噂される
事故物件に住んでいると、「あそこの部屋の人…」と噂されることもあります。
ときに、好奇の目で見られたり、無用な偏見を持たれてしまうことも。
地域との関係を大切にしたい人にとっては、こうした精神的プレッシャーが大きなデメリットになるでしょう。
事故物件に住むメリット
事故物件というと「怖い」「不安」といったマイナスイメージが先行しがちですが、実は人によっては魅力的な選択肢となることもあります。
とくにコスト面や設備環境においては、通常の物件よりもお得に暮らせる可能性も。
ここでは、事故物件に住むことで得られる具体的なメリットをご紹介します。
家賃が安い
事故物件の最大のメリットは、やはり圧倒的な家賃の安さです。
同じエリア・間取りでも、相場より20~30%ほど安く設定されていることが多く、初期費用も抑えられるケースがあります。
予算重視の人や一時的な住まいとして考えている人にとっては魅力的です。
徹底的にリフォームされている事が多い
心理的瑕疵を緩和するため、事故物件には大規模なリフォームが施されることが一般的です。
特に気になる臭いやシミなどの痕跡を取り除くために、通常よりも丁寧な改修がされている場合も多く、内装が新しく綺麗なことも。
築年数の割に設備が新しい、というギャップにお得感を感じる人もいるでしょう。
事故物件の特徴8選
「この物件、何かおかしい…」と感じたとき、実はそれが事故物件だったというケースも少なくありません。
事故物件には特徴があり、それらを見極めることで事前に判断することが可能です。
ここでは、外観や条件面からわかる、事故物件にありがちな特徴を8つご紹介します。
告知事項の記載がある
物件情報に「告知事項あり」と記載がある場合、その物件は高確率で事故物件です。
他にも、直接「事故物件」と表現されたり「訳あり物件」と明記されていることもあります。
これは入居者の心理的な不安を和らげるため、不動産会社が説明義務を果たすために用いられます。
似た間取りの物件より3割ほど賃料が安い
告知事項の記載がなくても、周辺相場より安い賃料の物件には注意が必要です。
同じ建物でも方角や広さなどの条件が異なるため、各部屋で家賃が異なるのは当然。
しかし、賃料が他と比べて明らかに安い部屋は、事故物件である可能性が高いです。
相場より30%以上安い場合は、一度詳細を確認したほうがよいでしょう。
一部だけリフォームされている
ドアや壁、クローゼットなど特定の一部分だけ新しくなっている物件も要注意です。
体液や血液が染み込み除去できなかった、または直接的な痕跡が残っていた場所の可能性があります。
全体的に古いのに、一部だけ新しい場合は確認が必要です。
マンション(アパート)名が変わっている
物件の所有者が変わっていないにもかかわらず、マンション名が変更されていた場合は、事故物件の可能性が高いです。
ネット社会では過去の事件がすぐ検索されるため、過去のイメージを払拭するために改名されることがあります。
気になる場合は、旧名称を調べてみましょう。
花を添えられている場所が近い
物件周辺や敷地内に花束が供えられている場合、人が亡くなった現場である可能性があります。
また、共有部にお札が貼られているなど、明らかに何かがあったと感じる要素があれば注意が必要です。
前に住人がすぐ退去している・当分入居者が来ない
短期間で退去する人が続いていたり、長期間空室のままになっている部屋も要警戒です。
特に人気エリアで長期空室となっている場合は、何らかの心理的瑕疵があると見て間違いありません。
事故物件では「すぐ退去→しばらく空き室」のパターンが多く見られます。
事故物件は「大島てる」でわかる?
事故物件の情報を調べる手段として有名なのが、事故物件情報共有サイト「大島てる」です。
全国の事故物件情報が地図付きで掲載されており、誰でも閲覧可能です。
ただし、これはあくまでユーザー投稿型の情報サイトなので、誤情報や更新遅れがあることも。
参考にはなりますが、契約前には不動産業者への確認も欠かせません。
事故物件住みます芸人「松原タニシ」さんとは?

出典:https://www.shochikugeino.co.jp/talents/matsubaratanishi/
| 本名 | 松原 高志(まつばら たかし) |
| 所属事務所 | 松竹芸能所属 |
| 通称 | 事故物件住みます芸人 |
| 作品 | 映画「事故物件 恐い間取り」シリーズ書籍「ボクんち事故物件」シリーズ書籍「恐い食べ物」書籍「事故物件怪談 恐い間取り」シリーズ |
事故物件に実際に住み、その体験を発信している芸人が「松原タニシ」さんです。
松竹芸能所属のピン芸人で、「事故物件住みます芸人」として広く知られています。
北野誠さんの番組「北野誠のおまえら行くな。」出演後の打ち上げをきっかけに、事故物件への居住を始め、様々な怪異体験を重ねてきました。
その体験を元に書籍『事故物件怪談 恐い間取り』を出版し、2020年には映画化。
2025年7月には続編も公開中です。
事故物件に対して「怖い」だけではなく、実際の暮らしや心構えを伝える人物として注目されています。