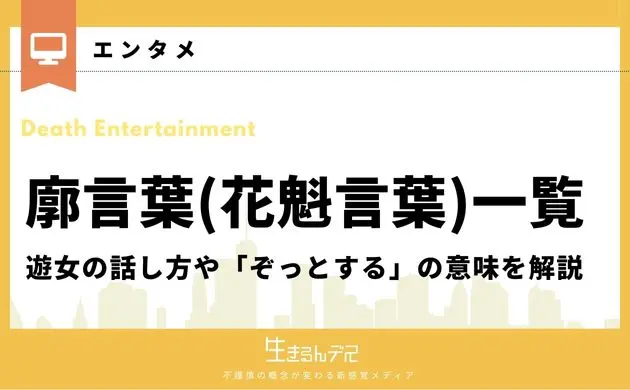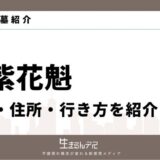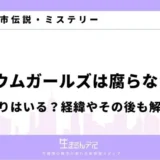江戸の花街で使われていた「廓言葉(くるわことば)」は、遊女たちが客をもてなすために生み出した美しく独特な話し方です。
今ではあまり聞かれませんが、その一部は意外と現代にも残っています。
この記事では、代表的な廓言葉の一覧や意味を紹介しながら、「ぞっとする」「あちき」など印象的な表現の背景を見ていきましょう。
廓言葉(くるわことば)とは
廓言葉とは、江戸時代の遊郭という特殊な空間で生まれた、遊女たちのおもてなしの言葉です。
日常とは異なる世界を演出するため、独自の語尾や言い回しが使われ、客に夢のような時間を感じさせる工夫がなされていました。
また、廓言葉には、身分差や感情を直接表に出さないための配慮も含まれており、言葉づかいによって距離感を保つ技術でもあったのです。
接客術と文化が融合した、まさに言葉の作法といえるでしょう。
廓言葉の一覧表
ここでは、遊女たちが実際に使っていた代表的な廓言葉をまとめました。
一見すると意味がつかみにくい言い回しも多いですが、どれも当時の情緒や遊郭文化が色濃く反映された表現ばかりです。
言葉づかいひとつに、距離感・気遣い・遊び心が込められていたことがわかります。
それぞれの意味を知ることで、より深く廓の世界を感じられるはずです。
| あちき・わちき・わっち | 私は~ |
| ~ありんす・~ござりんす | ~です |
| いいなんすな | 言わないでください |
| いりんせん | いりません |
| おさればえ | さようなら |
| おっせえす | おっしゃいます |
| おゆかり様 | 馴染みの客 |
| 金茶金十郎 | 馬鹿者・たわけ者を指す |
| ~ござりんせん | ~ではありません |
| さし | 事情があって会いたくない客 |
| 塩次郎 | うぬぼれが強い人 |
| ~しておくんなんし | ~してください |
| ~しておくんなんし | ~してください |
| ~しなんす | ~します |
| しわ虫太郎 | ケチな客 |
| 好かねえことを | 嫌なことを |
| ぞっとする | タイプの客を見つけた |
| 七夕 | バタバタうるさく歩く客 |
| ~なんざんす? | ~なんでございますの? |
| ~なんし | ~ください |
| 主さん | あなた |
| 武左(ぶざ) | 常に威張っている客 |
| ほんざんす | 本当です |
| 間夫(まぶ) | 良い男・本命の男 |
| 見なんし | 見てください |
| 野暮(やぼ) | センスのない男客・田舎者 |
現代でも使われる廓言葉
遊郭文化の名残をとどめる言葉は、実は今も私たちの暮らしの中にひっそりと息づいています。
ここでは、現代でも使われる代表的な廓言葉を見ていきましょう。
あがり
「もうあがった人」「この部屋はあがりです」など、今でも耳にする「あがり」は、廓言葉では「引退」や「終わり」を意味する言葉でした。
遊女が身請けされて遊郭を離れることを「あがり」と呼び、そこには自由になる、人生をやり直すといったニュアンスも込められていたのです。
また、家屋の造りに使われる「上がり框(かまち)」も、客が土間から座敷へ「あがる」という動作に由来しており、この言葉の広がりを感じさせます。
もてる
「異性にもてる」という言葉は、元々は遊女たちが「もてなす」ことから派生したとされます。
かつて遊郭では、上客に対して手厚くもてなすことが「もてる」と表現され、その人柄や振る舞いが遊女から評価されていたのです。
次第に「好かれる人」や「人気のある人」を意味するようになり、現在の「モテる」の語源のひとつとして語られるようになりました。
馴染み
今でも「馴染みの店」や「馴染み客」という表現はよく使われますが、これももとは遊郭の言葉です。
遊女にとって「馴染み」とは、何度も足を運んでくれる特別なお得意さまのことを指していました。
初対面の「新造」とは異なり、馴染みの客とは心の距離が縮まりやすく、信頼関係も築かれていたのです。
現代においても「親しみがある」「通い慣れた」という意味で自然と使われています。
廓言葉はお店ごとに使い分けられていた?
実は、ひとくちに廓言葉といっても、店ごとに独自の表現や言い回しが存在していました。
ここでは有名な四つの店を例に、それぞれの特徴を見ていきましょう。
扇屋
吉原の中でも名門とされた「扇屋」は、格式を重んじる老舗遊郭でした。
花魁たちには「~ありんす」など、伝統的で上品な廓言葉の使用が求められ、感情をあからさまに出さず、言葉の間や響きで客をもてなすことが重視されたのです。
控えめながらも洗練された言葉づかいは、接客そのものを芸の域に高め、空間全体に品格と非日常の空気を漂わせていました。
玉屋
「玉屋」は、華やかで艶のある花魁たちが揃っていたことから、やわらかく優美な話し方が特徴でした。
「~しておくんなんし」「おっせえす」「見なんし」など、心配りを感じさせる丁寧な言葉を使い分けながら、芝居のような演出で客を包み込んでいたのです。
語調の緩急や語尾の工夫により、客の身分や雰囲気に合わせた巧みな接客がなされていた、粋と情緒の融合した遊郭でした。
丁子屋
職人や町人など、庶民層の客が多く訪れた「丁子屋」は、親しみやすい接客が魅力の遊郭でした。
「なんし」「~しなんす」など、やわらかい語感の廓言葉が多く使われ、格式ばらずとも相手に安心感を与える対応が特徴です。
距離を感じさせない言葉づかいの中にもしっかりとした礼儀や心遣いがあり、人情味を求める客から高く支持されていました。
松葉屋
「松葉屋」は、教養ある遊女が多く在籍していたことで知られており、言葉にも知的な美しさが感じられる遊郭でした。
「ほんざんす」「ござりんす」などを使い分け、言葉の響きや余韻で客の心をくすぐるような語り口が特徴です。
知的で洗練された応対により、客に「自分は選ばれた存在だ」と思わせるもてなしが徹底され、言葉が一種の芸術として成立していた店でした。