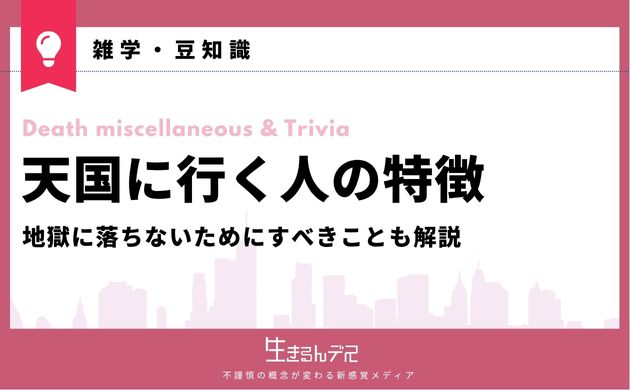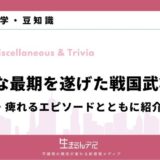天国に行く人には、どんな特徴があるのでしょうか。
私達の死後には、どんな世界が待っているのか分かりませんが、できれば地獄ではなくて天国に行きたいですよね。
この記事では、天国に行ける人の特徴や、地獄に落ちないためにどうしたらいいのかを解説します。
天国に行く人の特徴3選!
天国に行く人の特徴が表れるのは、心です。
死んだ後、肉体は滅びてしまいますし、生前にいくら多くの財産を持っていても使えません。
天国に行けるか行けないかは、生きている間の心の持ち方次第と言えるでしょう。
では、どのような心を持つ人が天国に行くのでしょうか。
心が綺麗な人
天国に行く人の特徴で大切なのは、心が綺麗なことです。
人が生まれる前の魂は天国にあり、自分で決めた目的を果たすために、綺麗な心を持ってこの世に生まれてくると言われています。
そして死後は天国に戻ることになっているのですが、もし生きている間に心が汚れてしまうと、美しい天国には戻れなくなるのです。
人の立場になって物を考えたり、助けが必要な人に救いの手を差し伸べたりするような「綺麗な心を持ち続けた人」だけが、天国に帰れるでしょう。
許す心を持っている人
許す心を持っていることは、天国に行く人の大きな特徴と言えるでしょう。
それは許す心があるかないかで、オーラの美しさを左右するからです。
人は誰でも、嫌いな人や自分と合わない人、羨ましいと思う人がいるもの。
その人達を憎んだり妬んだりしている間は、心がネガティブな気持ちで満たされてオーラが暗くなるため、天国に行けなくなるのです。
しかし、そんな相手を許せる心のゆとりがある人の周りには「美しいオーラが漂う」ので、天国に行けるようになります。
明るくのびのびと生きている人
明るくのびのびと生きている人は、天国に行きやすいかもしれません。
明るく自由に生きている人は前世でいいことをしたので、現世で人間関係などの環境に恵まれている可能性があります。
自分らしく寿命を全うした後は、天国に行けるでしょう。
逆に前世で悪いことをした人は、現世で難しい問題が次々と発生し、前向きに生きられないまま苦しい日が続きます。
ただし、今は辛い思いをして明るく生きていない人でも、強い心で困難を克服し「自分らしさ」を取り戻せば、天国への道が開けるでしょう。
そもそも天国ってどんなところなの?
天国はキリスト教に出てくる表現の一つで、信者の霊魂が永遠の祝福を受けられる理想的な場所とされています。
仏教には天国という表現はありませんが、人が亡くなった後に行けると言われる「極楽浄土」と呼ばれる場所があります。
仏教における極楽浄土とは、煩悩を忘れて仏になるために用意された場所です。
極楽浄土は煩悩やけがれがない場所で、そこにいると一切の苦しみやストレスを感じることがありません。
美しい宮殿や清らかな水で満ちた池があり、池のほとりには蓮華の花が咲き誇って芳しい香りを放っています。
地獄に落ちないためには?全員が地獄行きって本当?
天国に行く人の特徴に自分が当てはまらなくても、地獄には落ちたくないですよね。
しかし仏教には、破ると地獄に落ちるという厳しい戒律があり、その基準では普通に生きているだけで人間は全員地獄行きになってしまうのです。
ただし、この教えの背景には、その時代の人々が極楽浄土を目指すようにするため、わざと恐ろしい地獄を描いたとも考えられます。
したがって、現代に生きる我々があまり深く考える必要はないかもしれません。
最後は、地獄に落ちないために守るべきと言われている戒律と、守らないと落ちる地獄を紹介します。
殺生をしない
地獄は八段階あると言われており、一番罪が軽い人が行くのは等活地獄です。
等活地獄に落ちるのは生きている間に殺生をした者で、動物はもちろん植物の命を奪った者でも、この地獄に落ちるとされています。
等活地獄に落ちると、鉄の爪が生え周りの者が憎らしく見えるようになるので、お互いに鉄の爪でつかみ合う喧嘩をして、肉も骨も粉々になるまで戦い続けます。
しかし、粉々になった後でも定期的に肉体が再生されて、1兆6千億年の間戦い続けるのです。
嘘をつかない
八段階の地獄は罪を重ねる毎に、より辛い地獄に落ちます。
生前に嘘をついた人は、等活地獄より苦しい大叫喚地獄に落とされます。
大叫喚地獄は、嘘をついた罰として火で熱した針で舌を刺され、声が出せなくなるのが特徴です。
さらに、舌を抜かれたり目玉をくりぬかれたりするのですが、抜かれた舌や目は再生するので、何度も苦しい思いをすることになります。
また、生前に嘘の噂を広めて人を傷つけた人は、より恐ろしい焦熱地獄に落とされて、地獄の業火であぶられるでしょう。
お酒を飲まない
お酒を飲んだ人は、叫喚地獄に落ちると言われています。
叫喚地獄は熱い鉄板の上を歩かされたり、大きな鍋で煮られたりする地獄です。
また、口から熱い溶けた金属を流し込まれ、身体の内部も焼き尽くされます。
仏教には「不殺生」(殺さない)・「不偸盗」(盗まない)・「不邪淫」(不貞しない)・「不妄語」(嘘をつかない)と「不飲酒」の5つの戒めがあります。
お酒は平常心を失わせ、他の戒めも守れなくなるため、飲んではいけないとされているのでしょう。