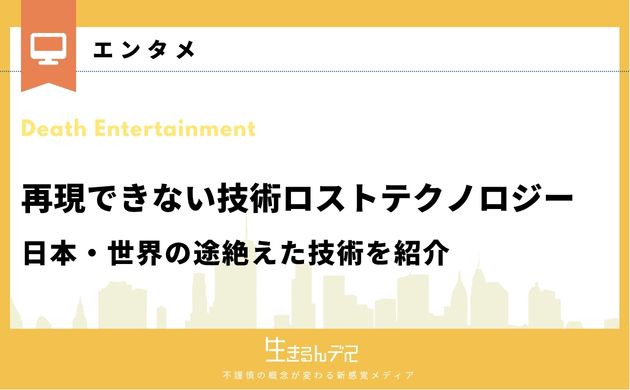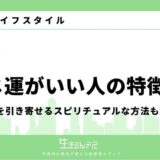日々技術は進化しており、新たな発見や画期的なアイテムが次々に誕生しています。
その一方で、失われている技術も存在しており、現在では再現不可能なものも数多く存在しているのです。
この記事では、かつて日本や世界に存在していた優れた技術の中でも、現在では再現できないロストテクノロジーに絞って紹介します。
再現できない技術ロストテクノロジー10選|日本
私たちの住む日本でも、失われた技術は数多くあります。
時代の変化や後継者問題など、さまざまな問題により失われた技術ですが、どれも当時の日本を支えてきたものばかり。
こちらでは、日本国内の現代では再現できない技術「ロストテクノロジー」を紹介します。
古刀(日本刀)
武士の象徴でもある日本刀。
そんな日本刀は大きく分類すると、慶長元年(1596年)以前に作られていた「古刀」と慶長元年以降に作られるようになった新刀に分けられます。
そのうち、古刀の製法は未解明な部分や新刀とは異なるところもあり、詳しい製法は失われてしまいました。
切れ味が鋭く、新刀よりも折れにくい強靭な特性をもつ古刀ですが、現代のテクノロジーをもってしても再現は不可能といわれています。
そのため、現存している古刀の多くが、重要文化財や国宝に指定されています。
2mmの銅鐸
銅鐸とは、弥生時代に作られていた青銅製の紋様が刻まれているベルのような形のもの。
構造から見て、鈴や鐘のように鳴らすものといわれていますが、作られた目的は現在も解明されていません。
また、厚さ2・3mmほどの銅鐸を当時の技術で製造するのは難しいといわれており、謎の多いロストテクノロジーです。
熟練の技術者が当時の製法で再現を試みても、厚さ5mmほどが限界とされており、今日まで発掘された厚さ2mmの銅鐸の再現には至っていません。
益田岩船(ますだのいわふね)
益田岩船とは、奈良県橿原市白橿町の岩船山の頂上近くにある巨大な岩のこと。
奈良県指定遺跡に指定されている岩で、南西11m・南北8m・高さ4.7m・重さおよそ800tもある非常に大きな岩です。
岩には加工されている跡があるものの、その目的や起源は全く分かっていません。
さらに、岩の切り出しはもちろん、構築や運搬手段についても解明されておらず、謎の多い岩として知られています。
高砂染(たかさごぞめ)
江戸時代の頃に、姫路藩(現:兵庫県)で誕生した染め物「高砂染」。
相生の松と吉祥紋を組み合わせた模様と多彩な色使いが特徴的で、幕府や朝廷にも献上されるほどの品でした。
しかし、姫路藩が消滅したことにより技術の維持が困難となり、昭和初期には失われてしまったようです。
幻の染め物として知られる高砂染ですが、高砂市の「エモズティラボ」が復元に取り組み、2019年に約100年ぶりの復活を成し遂げました。
紅板締め(べにいたじめ)
紅板締めは、模様が刻印された板に生地を挟んで染める染色技法のこと。
紅花を染料に使用した生地は鮮やかな赤色をしており、白色の桜や菊などの模様が映えます。
襦袢(じゅばん)や間着(あいぎ)に使われており、浮世絵などにも紅板締めと思われる下着が描かれています。
明治初期には生産も多かったですが、型染めが主流になったことにより紅板染めは衰退していきました。
幻となった染色技法ですが技術の発展に伴い、製法などが解明され始めています。
麻酔薬
「通仙散」は江戸時代の外科医・華岡青洲が開発した麻酔薬で、1804年には世界初となる全身麻酔の手術の際にも用いられています。
通仙散は、曼陀羅華(チョウセンアサガオ)のほか、数種類の薬草を用いて作られているとされていますが、具体的な配合・使用方法については記録が残されていません。
20年の歳月をかけて作られた秘伝の薬品ではありましたが、後に伝来した麻酔薬の普及により製法自体も失われました。
和算
「和算」は、江戸時代に発展した日本独自の算術のこと。
中国の伝統的な算術方法を基盤としており、庶民や武士など幅広い人々に広まっていきます。
しかし、明治に入ると和算は衰退していき、1872年の学制の発布では西洋数学が採用され、正式に和算は廃止されました。
戦艦大和
第二次世界大戦にて日本軍が製造した史上最強の戦艦「戦艦大和」。
長さ263m・排水量64000tと大規模な戦艦で、搭載された主砲も史上最大でした。
しかし、戦艦大和の最大の特徴でもある45口径46cm砲を3門まとめた3連装砲は、現在では再現不可能な技術といわれています。
素材や専用の設備なども再現できない要因ではありますが、何よりの課題は鉄鋼を削りだす職人がいないこと。
現代の技術では再現が難しく、戦艦大和は史上最大の戦艦・主砲として記録に刻まれています。
東京タワー
東京のランドマークである東京タワー。
そんな東京タワーの建設には、ロストテクノロジーといわれている「リベット打ち」が採用されています。
リベット打ちという技法には高い技術力と経験が必要で、溶接やボルト接合が主流の現代では失われつつある技術です。
戦後復興のシンボルとして建設された東京タワーですが、当時の製法で再現することはほぼ不可能といわれています。
型板ガラス
型板ガラスとは、片側に模様がついたロールの間に、ガラス溶解素材を通して模様をつけたガラスのこと。
かつては、どの家庭でも型板ガラスが使われていましたが、作り手不足によりロストテクノロジーとなりつつあります。
令和の時代でも、昭和レトロな雰囲気が可愛いと、あえて型板ガラスにする家庭もあるようです。
しかし、現代では量産が難しくなっており、古民家などから買い取ったものを加工して使うケースも少なくありません。
再現できない技術ロストテクノロジー10選|世界
日本国内だけでもたくさんの再現できない技術があるように、世界中にはたくさんの失われた技術「ロストテクノロジー」が存在します。
世界のロストテクノロジーにはどのようなものがあるのか、こちらで紹介します。
技術の進歩の裏にある失われた技術たちには、当時の人々の努力や工夫で溢れているのが特徴です。
この機会に、ロストテクノロジーに注目して時代の変化を感じましょう。
ダマスカス鋼
ロストテクノロジーとして有名な「ダマスカス鋼」。
古代インドで開発された金属で、インド産のウーツ鋼が原材料です。
主に刃物に加工されることが多く、ダマスカス鋼で作られた刀や剣は頑丈で切れ味が鋭く錆にも強いなどの特性を持ちます。
十字軍が活躍する時代では、王家の宝として高い評価を得ていました。
表面に木目状の模様が浮かび上がっている「見た目も美しい金属」でしたが、18世紀までには製造技術はほぼ途絶えています。
アンティキティラ島の機械
「アンティキティラ島の機械」は、アンティキティラ島近海の海中で発見された古代遺跡。
少なくとも37個以上の歯車が複雑に組み合わさってできており、専門家たちによると紀元前1~2世紀の産物といわれています。
長年、使用用途や複雑な技術について議論されてきましたが、天体や太陽系の動きを忠実に再現した機械であることが判明しました。
しかし、これほどの精巧な機械を作る技術は存在しないと疑問の声を上げる専門家も少なくなく、現代においてもここまで複雑な機械は作られていません。
ローマの水道
紀元前312年〜3世紀にかけて古代ローマで建設されていた「ローマの水道」。
地下に流れるものや水道橋になっているものなどさまざまな形式があり、石材の風化や積載物などにも対応する「都市や工業地への水の供給には欠かせないもの」となっています。
水の除菌まで行えるという優れた技術を有したローマの水道は、新しい水道の必要性がなくなったことから技術が途絶えてしまいます。
現代においてもローマの水道は多くの都市で使用され続けており、2000年以上という長い年月の間、ずっと水の供給を続けているのです。
兵馬俑(へいばよう)
兵馬俑とは、中国陝西省にある始皇帝陵の近くで発見された「兵士と馬をかたどった人形」のこと。
1974年に発見された兵馬俑は、なんと8,000体にもわたり最高等級となる中国の5A級観光地に指定されました。
ロストテクノロジーとされているのが、兵馬俑を分析したことで発見されたクロムメッキの技術の痕跡。
クロムメッキ技術は、1930年代のドイツで発明されたとされていますが、その2000年以上前の古代中国ですでに活用されていた可能性があったのです。
兵馬俑がもっていたクロムメッキの剣は、ロストテクノロジーやオーパーツなどといわれ現在も謎に包まれています。
ロシアンレザー
ロシアンレザーとは、19世紀のロシアにて貴族向けに製造されていた高級革製品。
貴重な高級輸出品としてロシア帝国では重宝されていましたが、ロシア革命とともに革の製造法が失われてしまいました。
現代でも流通することのあるロシアンレザーですが、これらは1986年に沈没した船内から回収されたものです。
海底に長い期間眠っていたため、状態の悪いものが多く、希少性の高い革製品として愛好家から愛され続けています。
Entombed
「Entombed (エントゥームド)」は、1982年にATARI2600から発売されたレトロゲームのこと。
縦スクロールで迷路をクリアする単純なゲームではありますが、ロストテクノロジーといわれているのが「迷路を自動生成するプログラム」です。
経路を含めてどのように迷路を生成しているのか、そのロジックは解析不能とされています。
現代に比べて、容量不足や技術的な問題から制約の多いレトロゲーム。
Entombedでは、解析不可能な謎のコードで容量不足などの問題を乗り越え、ゲームとして実現させているのです。
ダ・ヴィンチの円形戦車
「ダ・ヴィンチの円形戦車」は、中世イタリアの天才発明家レオナルド・ダ・ヴィンチが1485年頃に描いたとされている戦闘用車両のこと。
巨大な亀のような円錐型の装甲が特徴的ですが、現代の専門家によると実現困難とされる問題点がいくつも見つかっています。
しかし、レオナルド・ダ・ヴィンチは技術者としても天才的であったため、指摘するようなミスを犯すとは考えられません。
そのため、意図的に問題点の多い設計図を残し、後世に実現されないようにしたとする見方もあります。
プラチナ加工の技術
18世紀以降に本格的に研究されるようになったプラチナですが、実は南米では10世紀頃から広く用いられていました。
融点が1774度と非常に高く加工の方法も不明だったため、南米外に持ち出されるものの、価値のないものとして処分されていたそうです。
現代では、ジュエリーや医療、燃料電池など幅広い分野で活用されているプラチナ。
しかし、10世紀からあった南米のプラチナ加工技術が広まることはありませんでした。
F-14(イラン製)
F-14はアメリカ合衆国のグラマン社が開発した艦上戦闘機で、化け猫という意味の「Tomcat (トムキャット)」の愛称で知られています。
当時同盟国であったイランへF-14が納入され、1979年のイラン革命後も使用されました。
しかし、イランが反米の姿勢を強めたことから、F-14の純正部品を集めることができずロストテクノロジー化してしまいます。
リュクルゴスの聖杯
「リュクルゴスの聖杯」は、紀元4世紀頃の後期古代ローマ時代に製造されたガラスの杯。
光の反射角度によって色を変化させる神秘的で美しい仕掛けが施されており、この時代で同じような仕組みをもつ遺物は発見されていません。
リュクルゴスの聖杯のように色を変化させるためには、金属の粒子をナノレベルまで正確に計測する必要があります。
色を変化させるリュクルゴスの聖杯の発見は、古代ローマ時代にはすでにナノテクノロジー技術を有していたことを示しているのかもしれません。